脳・心臓疾患の労災認定に関し、必要な調査事項を取上げます。
脳・心臓疾患と労災
過労による脳・心臓疾患は、労災の業務上疾病として扱われる可能性があります(労基法施行規則別表第1の2第8号)。
脳・心臓疾患の労災認定基準は、すでに、取上げました。今回は、労災の認定に際し、必要な調査事項を取上げます。
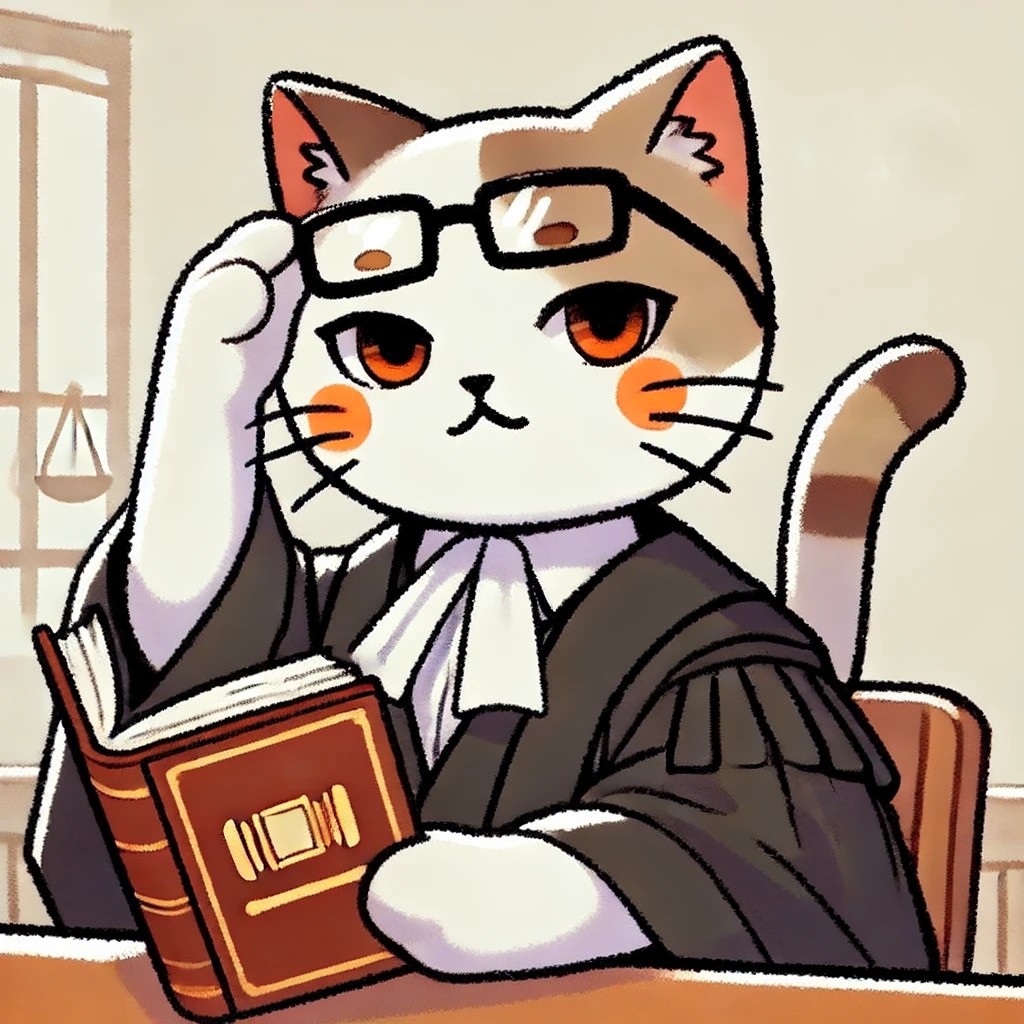
脳・心臓疾患の労災認定基準は、以下の記事参照
脳・心臓疾患の労災認定のために必要な調査事項
脳・心臓疾患の労災認定に関し、必要な調査事項は、以下の3つです。
脳・心臓疾患の労災認定のために必要な調査事項
①対象疾病の確認
②過重業務の確認
③危険因子の状態の確認
①対象疾病の確認
脳・心臓疾患の労災の認定に際し、出発点となるのは、発症した疾患名です。さらに、過重性の評価の起点になる発症時期の特定も必要です。
疾患名の特定
なお、認定基準の対象疾病以外の体循環系の各動脈の閉塞・解離は、基礎疾患の状況、業務の過重性等を個別に検討し、対象疾病と同様の経過で発症し、業務が相対的に有力な原因と判断できる場合は、「その他業務に起因することが明らかな疾病」(労基法施行規則別表第1の2第11号)として、業務上疾病として労災と認定されます。
発症時期の特定
脳・心臓疾患の発症は、血管病変等が破綻(出血)・閉塞した状態、循環異常を急性に来した状態をいいます。なお、自覚症状又は他覚所見が明らかに認められる状態です。
臨床所見、症状の経過等から症状が出現した日を特定し、発症日とします。
脳・心臓疾患の発症の前触れとなる前駆症状が認められ、前駆症状と発症した脳・心臓疾患との関連性が医学的に明らかな場合は、前駆症状が確認された日が、発症日となります。
②過重業務の確認
長期間の特に過重な業務、短期間の特に過重な業務への従事の有無、異常な出来事の有無を確認します。
労働時間の調査
長期間の過重な業務への従事の有無の確認は、発症前1か月間、発症前2か月間~6か月間の労働時間数、休日労働日数を確認します。
発症日から30日ごとに、発症1か月前、発症2か月前と順に遡って、発症6か月前までの労働時間数を確認します。
労働時間以外の負荷要因
勤務時間の不規則性、事業場外における移動を伴う業務、心理的負荷を伴う業務、身体的負荷を伴う業務、作業環境といった労働時間以外の負荷要因を確認します。
③危険因子の状態の確認
脳・心臓疾患が労災と認定されるには、業務による明らかな過重負荷が加わることで、血管病変等が自然経過を超えて著しく増悪したことが要件です。
血管病変等が、長い年月の生活の中で、徐々に形成・進行・増悪している状態だったのかを知るため、労働者の危険因子の状態を確認する必要があります。
職場での健康診断結果、医療機関の受診歴・カルテ等から危険因子の状態を確認します。