労働安全衛生規則が改正され、2025年6月1日から職場における熱中症対策が義務化されます。
職場における熱中症のリスク
ここ数年、猛暑の影響で、職場での熱中症発生リスクが高まっています。熱中症による死亡災害は、2年連続で30人を超えています。そのほとんどが、屋外作業で発生しています。
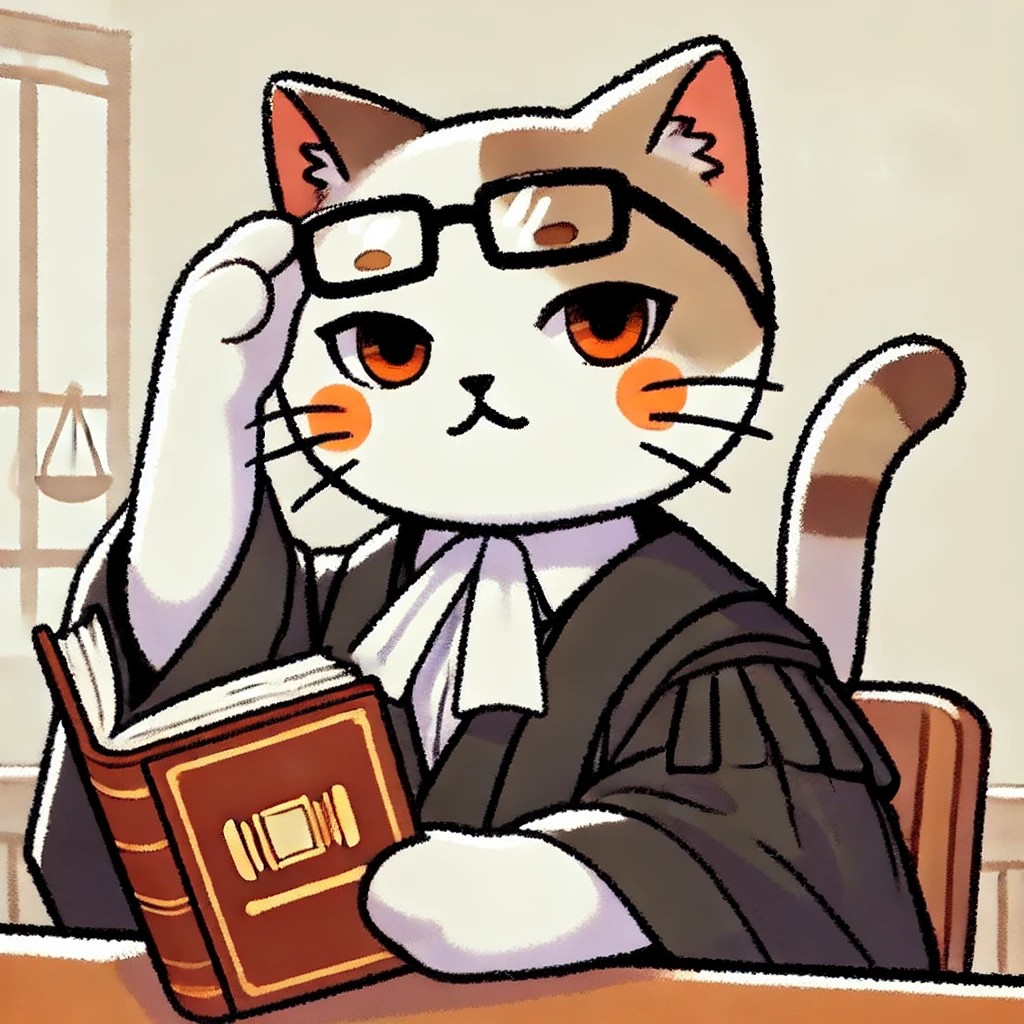
熱中症の労災認定については、以下の記事参照
このような状況を受け、労働安全衛生規則が改正されました。2025年6月1日から職場における熱中症対策が義務化されます。
初期症状の放置・対応の遅れが問題
熱中症が死亡災害になる割合は、他の災害の約5~6倍です。そのほとんどが、初期症状の放置などの対応の遅れげ原因です。つまり、初期の段階で異変に気づき、迅速かつ適切に対応できていれば、救われた命があった可能性が高かったのです。
そこで、現場において、死亡に至らせない又は重篤化させないための適切な対策の実施が必要とされます。特に、初期対応の強化が、熱中症対策が義務化されるに至った理由です。
「見つける」「判断する」「対処する」の義務化
熱中症対策の義務化のポイントが、現場の実態に即した具体的な対応として、以下のフローを強化することです。
- ①見つける
- 労働者の熱中症の兆候を「見つける」
- ②判断する
- 救急車を呼ぶ等の適切な措置を「判断する」
- ③対処する
- 救急車が到着するまで、作業着を脱がせ水をかける等、速やかに「対処する」
現場における対応
「見つける」「判断する」「対処する」ことによって、熱中症の重篤化を防止するために、以下の「体勢整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
熱中症のおそれがある労働者を「早期に見つける」体制の整備
熱中症の自覚症状がある労働者や、熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が、その旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知が義務付けられます。
単に報告を受けるだけでなく、職場巡視や声かけ、ウェアラブルデバイス等の活用により、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握する努力も求められます。
熱中症の初期症状は様々
熱中症の初期症状は様々です。「手足がつる」、「立ちくらみ・めまい」、「吐き気」、「何となく体調が悪い」などの自覚症状だけでなく、「イライラしている」、「呼びかけに反応しない」、「ボーっとしている」など、周囲から見て気づく症状もあります。
これらの症状に気づいたら、すぐに周囲の人や現場管理者に申し出ることの重要性を従業員に周知する必要があります。
労働者を把握した場合の「迅速かつ的確な判断・対応」のための手順作成と周知
熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能となるよう、以下の事項が義務付けられます。
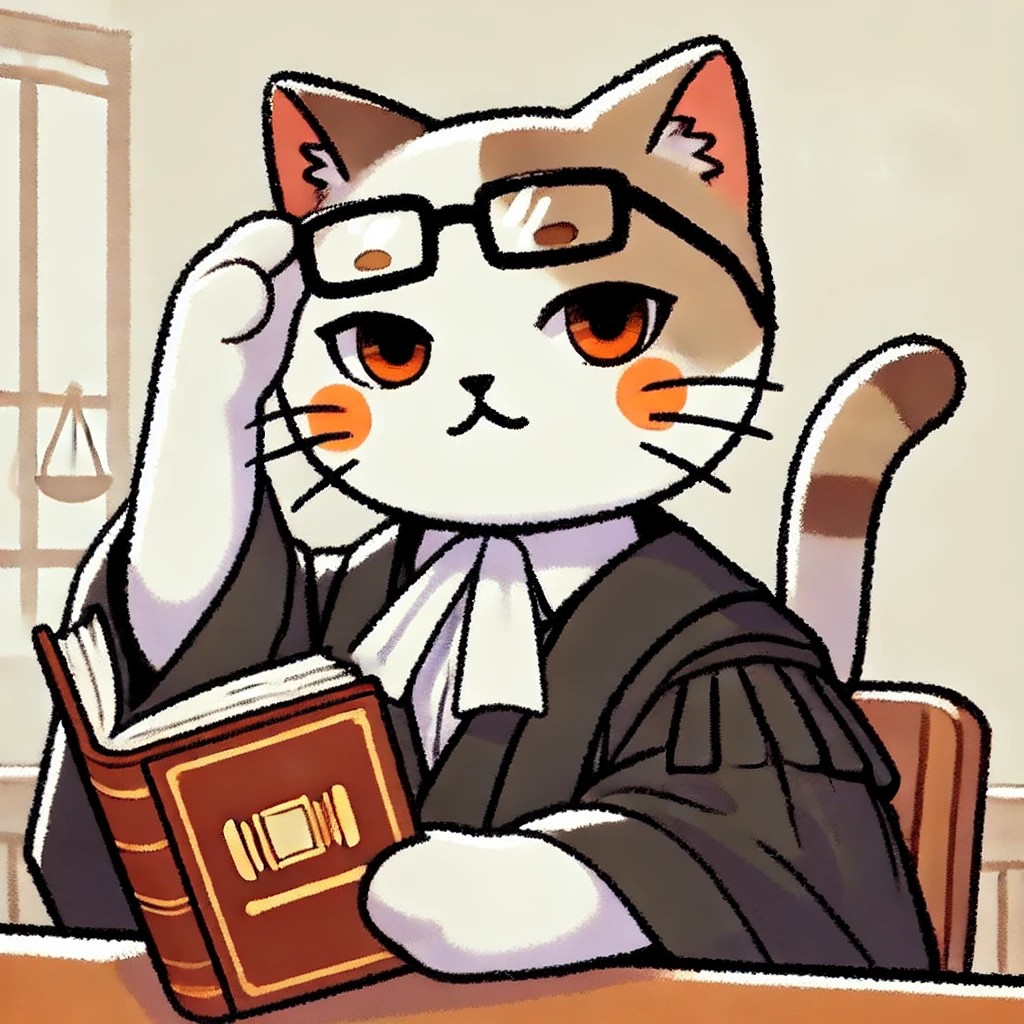
現場の実情にあった内容にすることが重要です。
熱中症対策義務化の対象となる作業環境
熱中症対策義務化の対象となる作業環境は、以下の①②を満たすものです。
熱中症対策義務化の対応は急務
職場における熱中症対策が義務化されるのは、2025年6月1日からです。それまでに、事業者は、作業環境における熱中症リスクを再評価し、早期発見のための体制整備、対応手順の作成、そして従業員への周知・教育を進める必要があります。
これらの対策を怠り、労働者が熱中症により被災した場合、安全配慮義務違反に基づく損害賠償が認められるリスクが高まります。
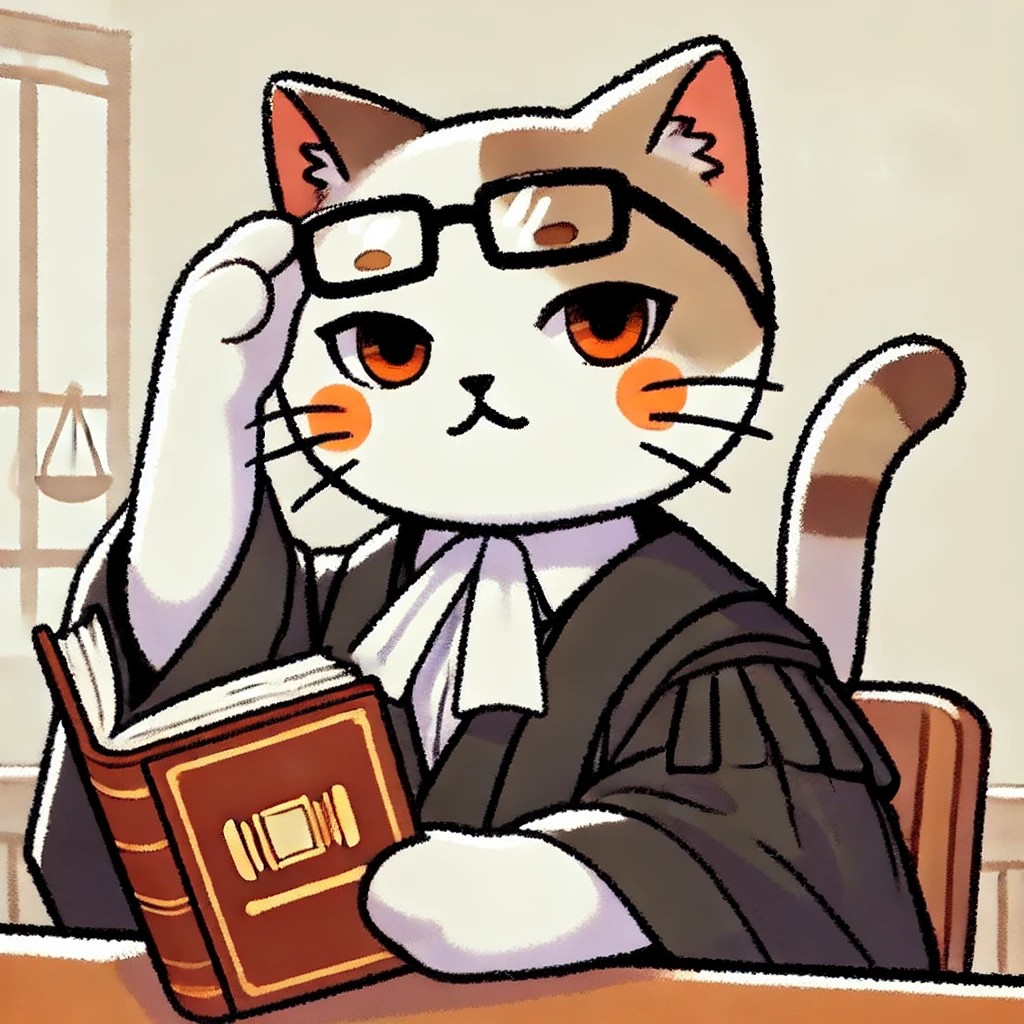
熱中症の安全配慮義務については、以下の記事も参照
熱中症対策は労災予防の重要な柱
熱中症対策は、法律で定められた義務を果たすだけでなく、労働者の命と健康を守り、ひいては企業の生産性維持や信頼確保にも繋がる重要な労務管理の一つです。熱中症対策体制を万全なものにしていただくことを強く推奨します。
改正法の内容や具体的な対応手順の作成についてご不明な点があれば、労災問題に詳しい弁護士や専門家に相談することをご検討ください。