首、肩や腕の痛みは、年齢や日常生活と密接に関連しています。過重な業務によって発症したと認められる場合は、労災と認められます。
首・肩がパンパン…

毎日パソコンで首も肩もパンパン…これで労災なんて言ったら笑われるかな?
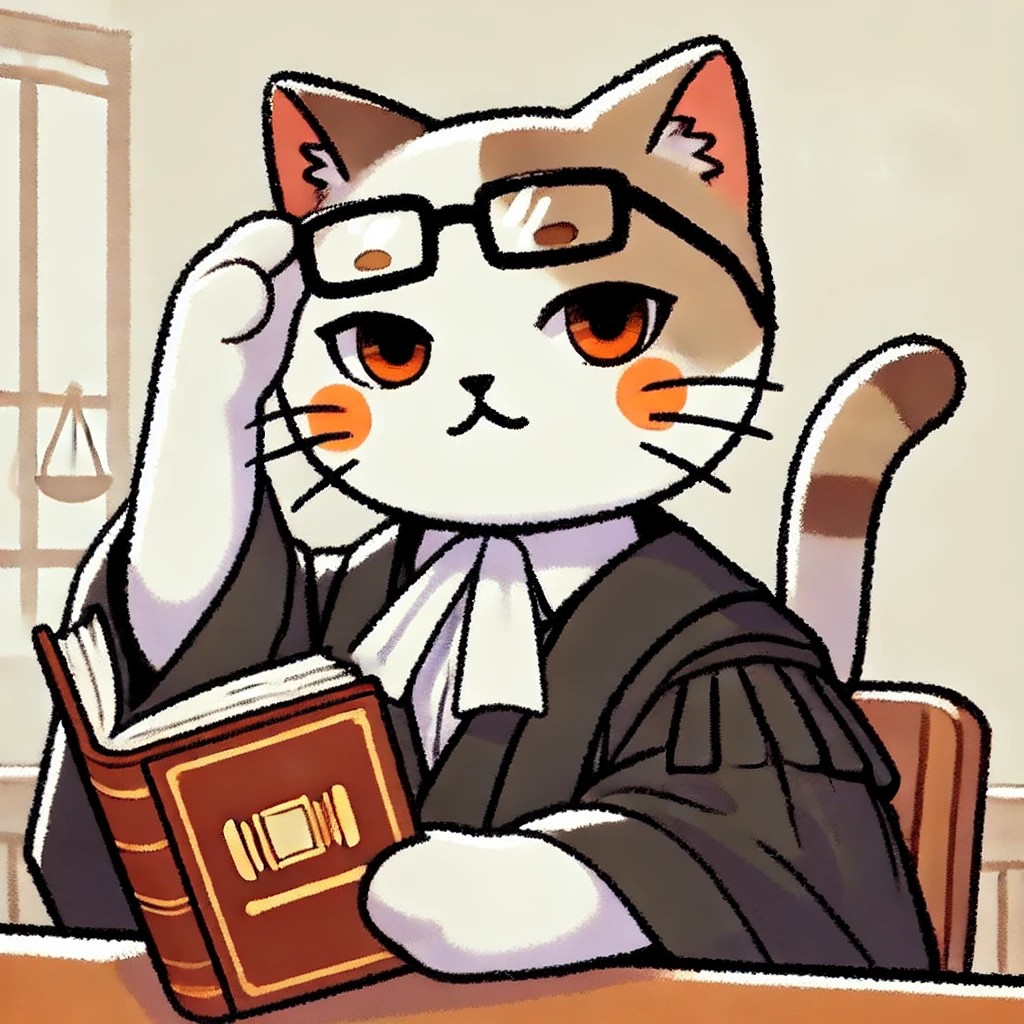
ただの肩こりは、さすがに労災と認められないよ。
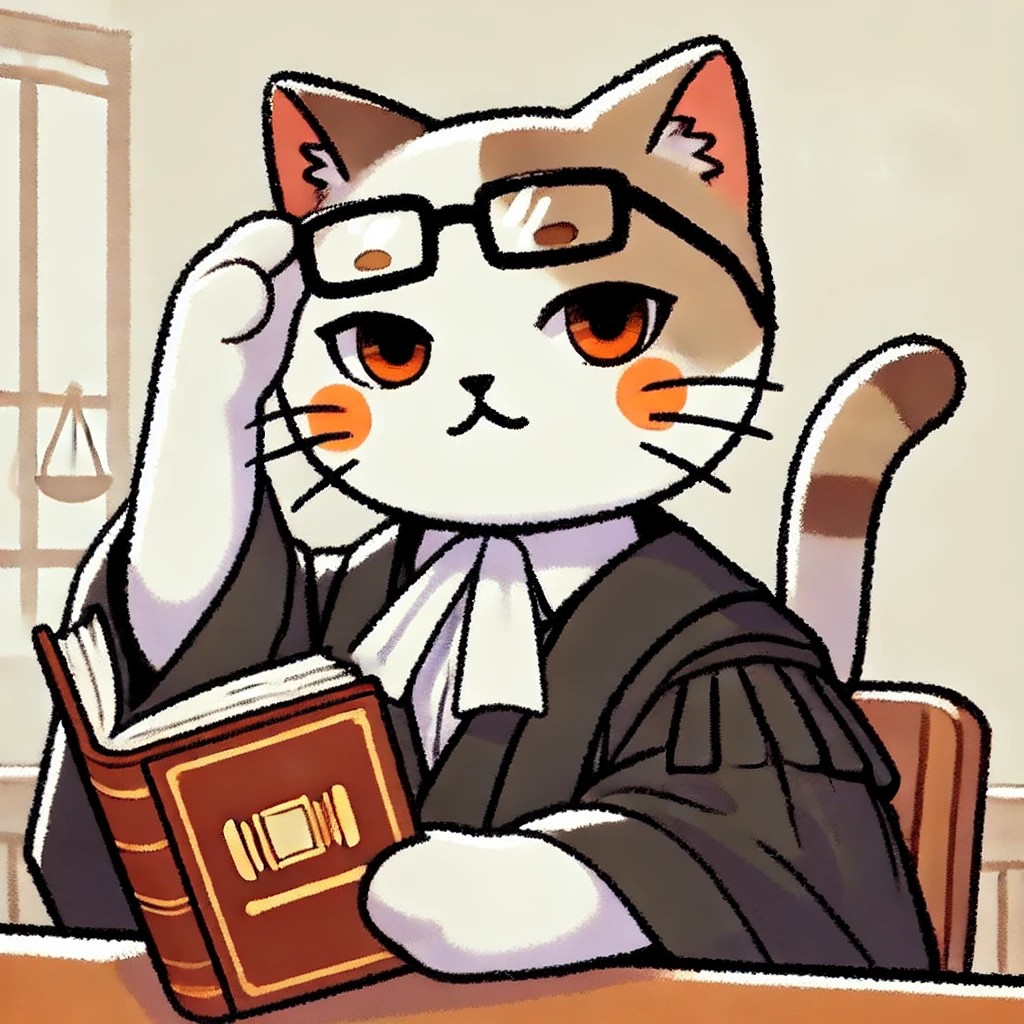
でも、過重な仕事が原因で発症した場合は、労災と認められることがあるよ。
デスクワークに従事している人は、多少なりとも首や肩の痛みを感じているでしょう。単なる肩こりや首のこりは、さすがに、労災になりません。しかし、過重な業務によって発症したと認められる場合は、労災と認定されることがあります。
首・肩の痛みと労災
首や肩の痛みは、「電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務による後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器の障害」として労災となる可能性があります。
厚労省によって、認定基準が定められています。
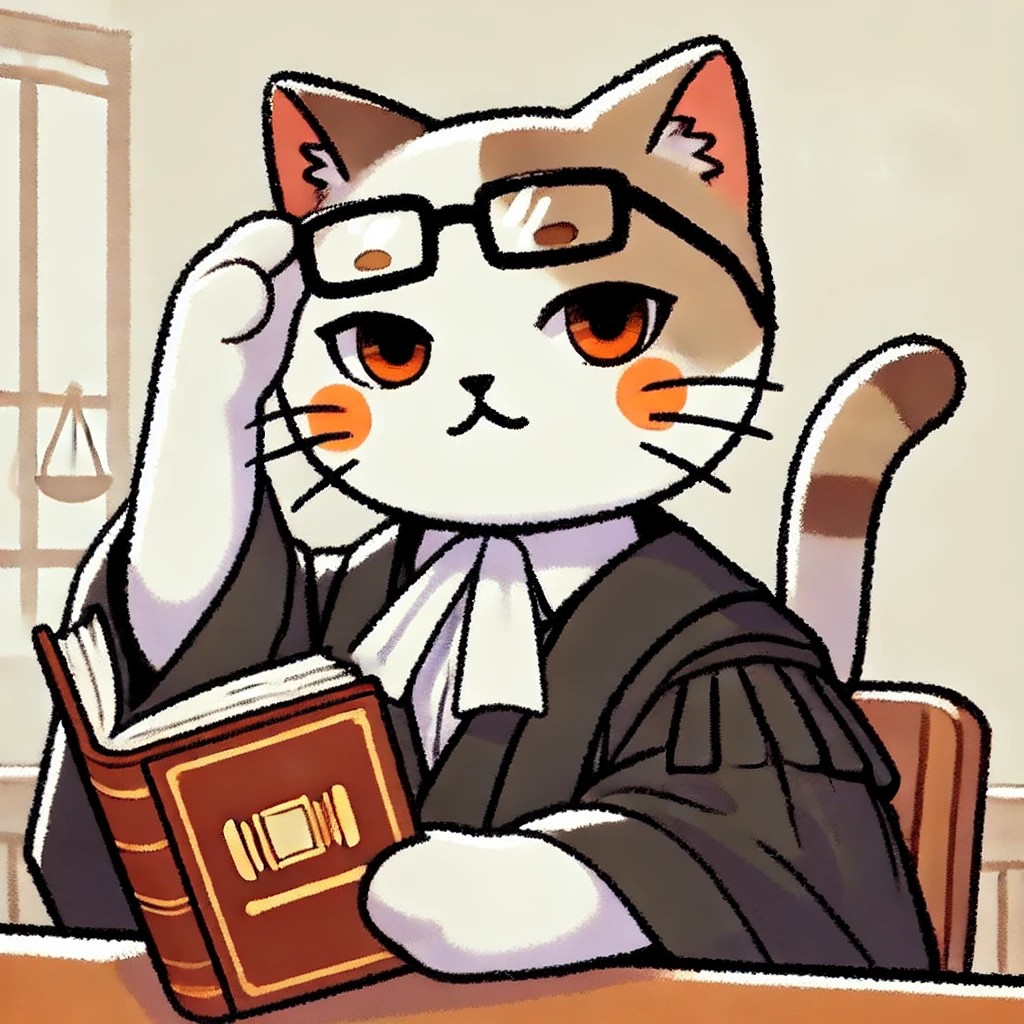
認定基準の詳細は、以下の「上肢障害の労災認定」を参照
上肢障害
労災の対象となるのは、首、肩、腕、手の運動器の障害です。これを上肢障害といいます。
上肢障害という疾病が存在するわけではありません。上肢等に過度に負担のかかる仕事が原因の疾病を総称して上肢障害と呼んでいます。以下のような具体的な疾病について、労災かどうかが判断されます。
上肢障害の例
①肘部管症候群
②回外(内)筋症候群
③手関節炎
④腱鞘炎
⑤頸肩腕症候群
上肢に過度の負担がかかる業務
上肢障害が、労災と認められには、上肢に過度の負担のかかる業務が原因で発症したことが必要です。
認定基準は、上肢に過度の負担のかかる業務を以下の4つに分類しています。
上肢に過度の負担のかかる業務
①上肢の反復動作の多い作業
②上肢を上げた状態で行う作業
③頸部、肩の動きが少なく、姿勢が拘束される作業
④上肢等の特定の部位に負担のかかる状態で行われる作業
①上肢の反復動作の多い作業
①上肢の反復動作の多い作業として、OA機器、VDT機器等の操作を行う作業や運搬・積込み・積卸し作業などが挙げられています。
②上肢を上げた状態で行う作業
②上肢を上げた状態で行う作業として、天井など上方を作業点とする作業などが挙げられています。
③頸部、肩の動きが少なく、姿勢が拘束される作業
③頸部、肩の動きが少なく、姿勢が拘束される作業として、検査作業が挙げられています。
④上肢等の特定の部位に負担のかかる状態で行われる作業
④上肢等の特定の部位に負担のかかる状態で行われる作業として、保育、看護、介護作業が挙げられています。
労災認定のポイントは過重な業務
首や肩の痛みが労災と認定されるかのポイントは、過重な業務に従事していたか?です。通常のデスクワークによる肩こりや首のこりは、労災と認められません。
労災の請求の際は、業務がどれほど過重で、首や肩に負担がかかったのかを主張・立証することが重要です。
認定基準では、発症前の業務に対する量的な評価基準が定められています。
過重な業務
同じ職場の同種労働者と比較して、おおむね10%以上、業務量が増加し、その状態が発症前3か月程度続いている
業務量から過重性を判断できない場合で、以下の要因が顕著に認められる場合は、以下の要因も総合して、過重な業務かを判断します。
過重な業務の判断要素
①長時間作業、連続作業
②他律的かつ過度な作業ペース
③過大な重量負荷又は力の発揮が必要な作業
④過度の緊張
⑤不適切な作業環境
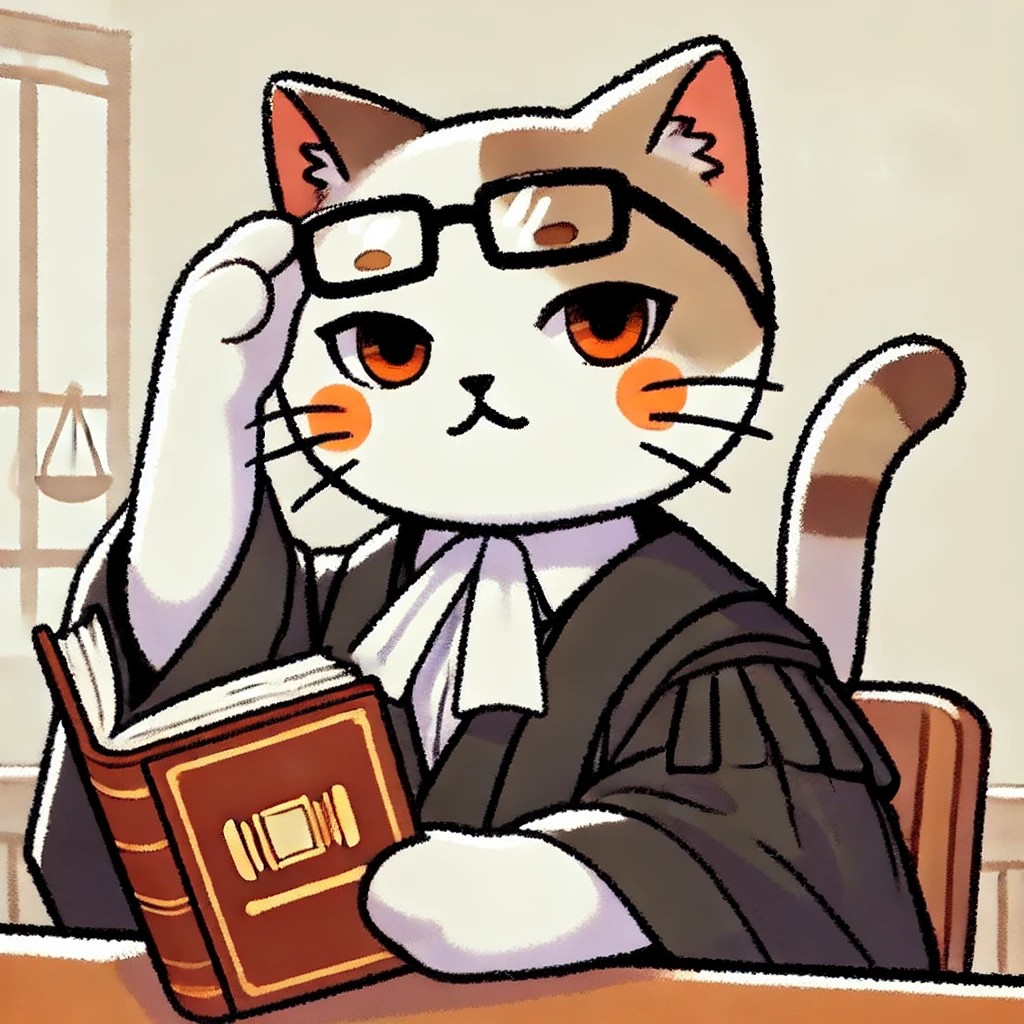
通常業務による負荷を超える一定の負荷が認められることが前提です。
首や肩の痛みは仕事が原因かなと思っている方へ
首や肩の痛みは、年齢や日常生活など様々な原因で発症します。首や肩に過度に負担のかかる仕事をしていて、過重な業務が原因で発症したと認められれば、労災と認定されます。
労災と認定されれば、労災保険から補償を受けられます。労災は、自分の健康と生活を守る手段です。また、会社に安全配慮義務違反がある場合は、損害賠償請求もできます。
労災と認定されるには、ポイントを押さえて、正しく主張・立証することが重要です。そのためには、専門家である弁護士にご相談ください。
首や肩の痛みは仕事が原因だと思うけどまだ労災の請求をしていない方、労災かどうかわからない方、会社に損害賠償請求したい方、まずは、お気軽にご相談ください。法律事務所エソラは、労災の初回相談無料です。
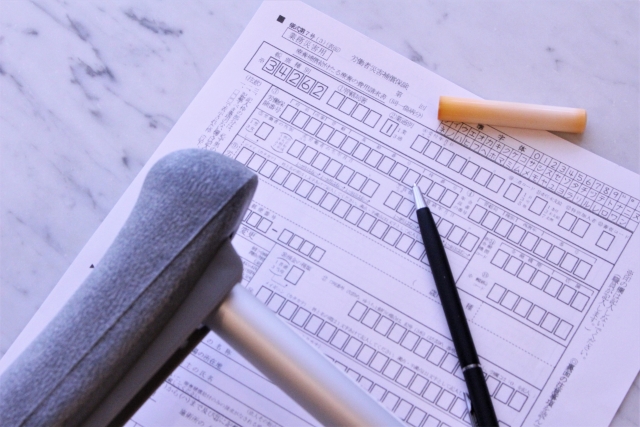
無料相談はこちら
労災の無料相談はこちらからお申込みください。