労災保険の給付の内、休業(補償)給付を取上げます。
休業(補償)給付
休業補償給付は、労働災害により、労働不能になった場合の賃金の喪失に対する補償として支給されます(労災保険法14条)。
通勤災害の場合は、休業給付といいます。支給要件・給付内容は、同じです(労災保険法22条の2)。
以下、休業補償給付について説明していますが、通勤災害の休業給付にも当てはまります。
休業補償給付の支給要件
労働者が①業務上の傷病による療養のため、②労働することができないことにより、③賃金を受けれないことが支給要件です。
療養のため
業務上の傷病の治療を目的とすることが要件です。治ゆ(症状固定)後の治療は、含まれません。
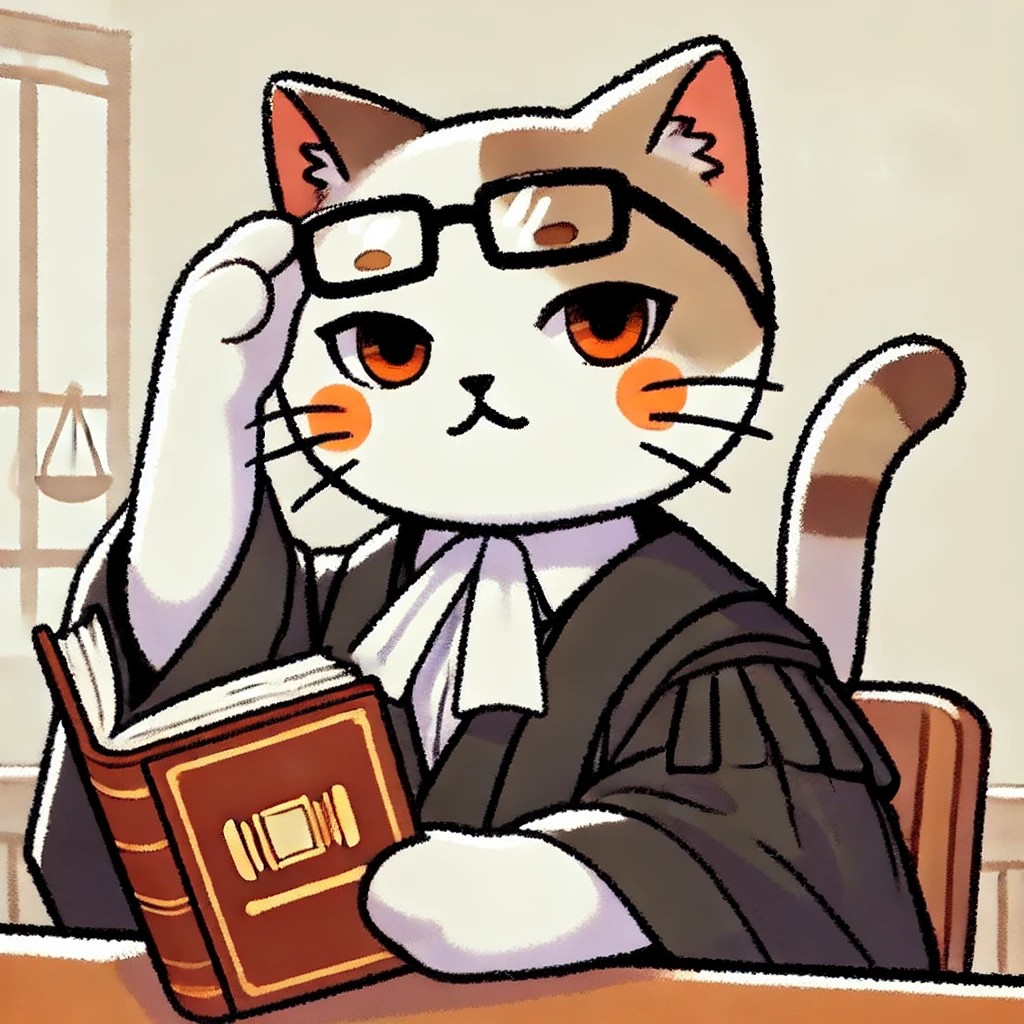
治ゆ(症状固定)の詳細は、以下の記事参照
労働することができない
療養上、労働することが不可能又は不適当な場合をいいます。
一般的な労働不能を意味します。つまり、労働災害前に従事していた労働はできないが、軽作業はできる状態であれば、この要件を満たしません。したがって、休業補償給付は受けられません。
なお、全部労働不能か一部労働不能かを問いません。たとえば、午前中に通院して、午後から出勤した一部不能の場合も休業補償給付の対象です。
賃金を受けれない
使用者から全く賃金を支払われていない場合だけではなく、一部しか支払われていない場合を含みます。
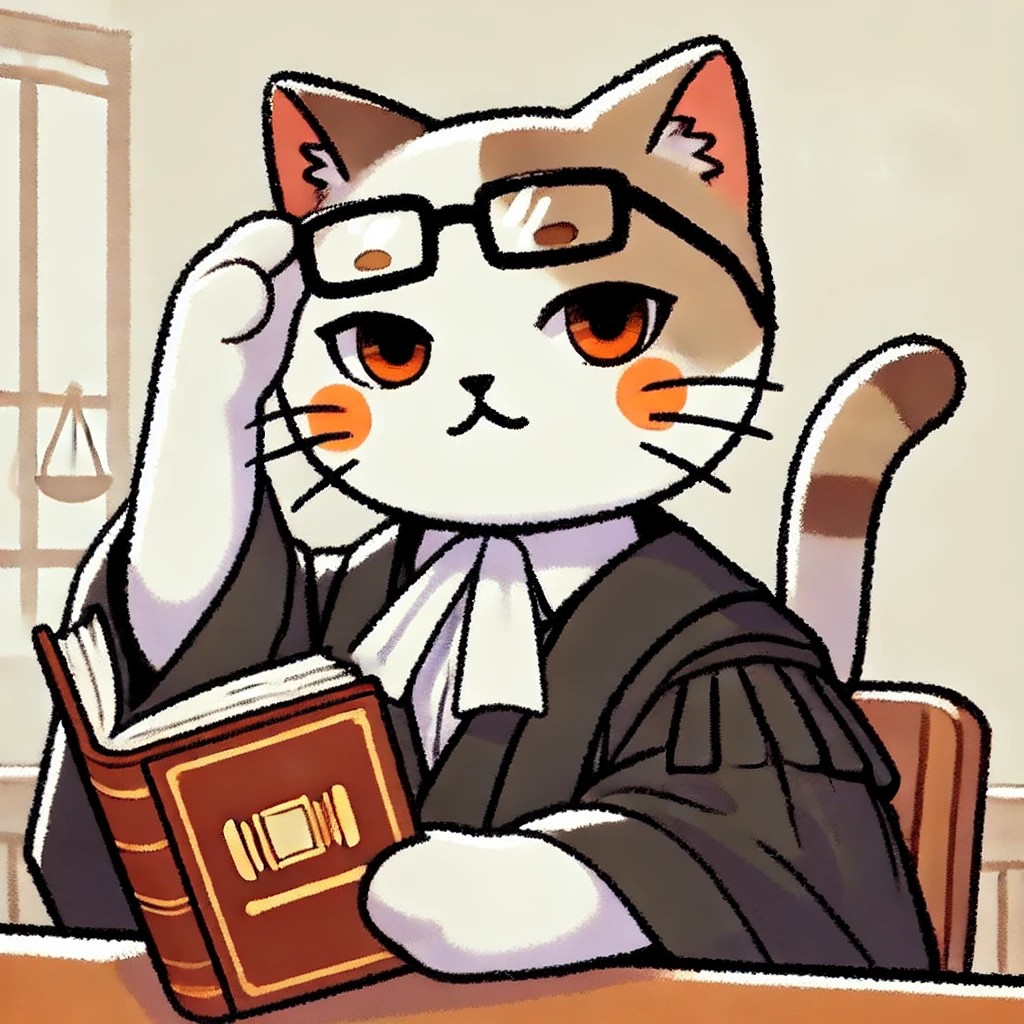
賃金が一部支払われた場合については、以下の「労災保険の休業(補償)給付と部分算定日」を参照
給付内容
給付基礎日額の60%が支給されます。
休業補償給付とは別に、社会復帰促進等事業に基づく休業特別支給金として給付基礎日額の20%が支払われます(労災保険法29条1項、50条、労災保険特別支給金支給規則3条1項)。
したがって、合計で給付基礎日額の80%が支給されることになります。
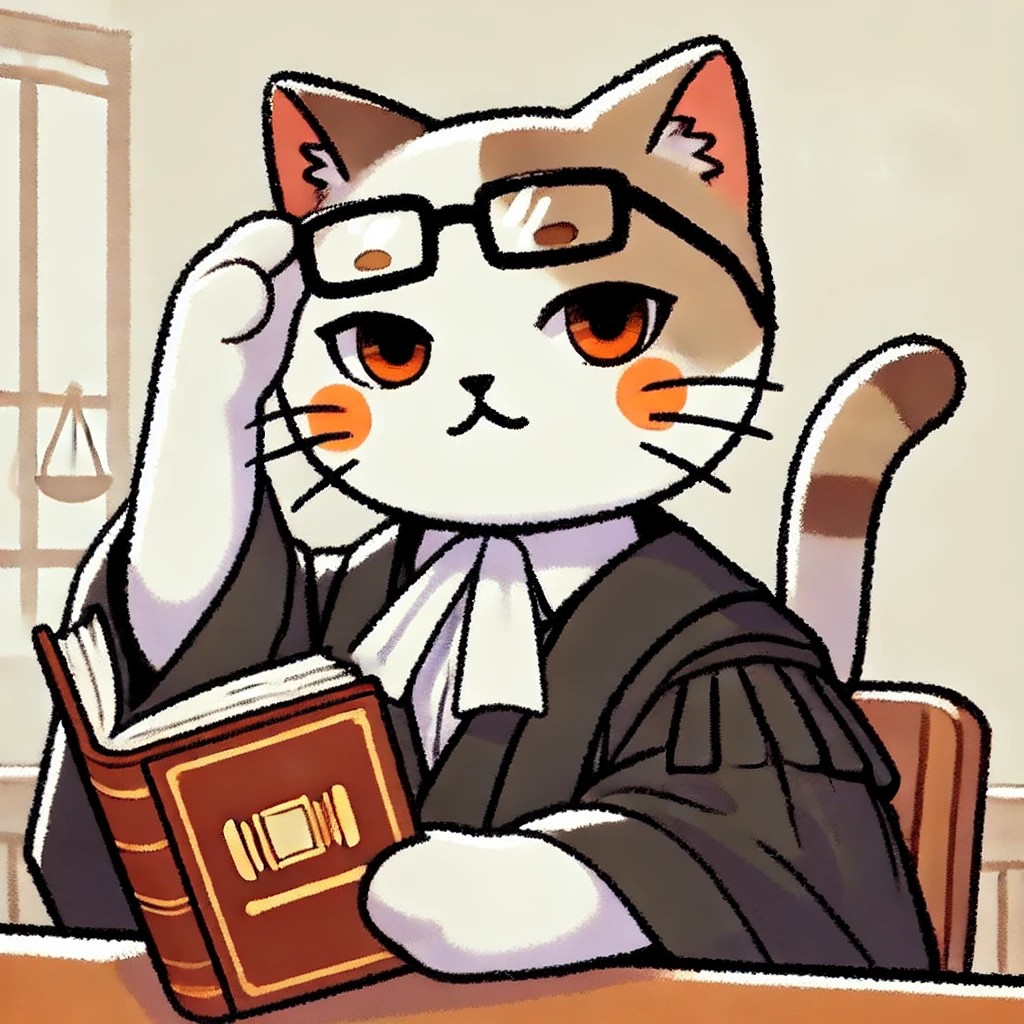
給付基礎日額の詳細は、以下の記事参照
給付基礎日額(労災保険の基礎)
労災保険の休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付など各種の給付は、給付基礎日額を基に金額が算出されます。労災の給付の基礎である給付基礎日額を解説します。
待期期間
休業補償給付は、労働者が労働災害による傷病の療養のため労働することができないため、賃金を受けない日の4日目から支給されます(労災保険法14条1項本文)。休業初日から3日間は支給されません。この3日間の期間を待期期間といいます。
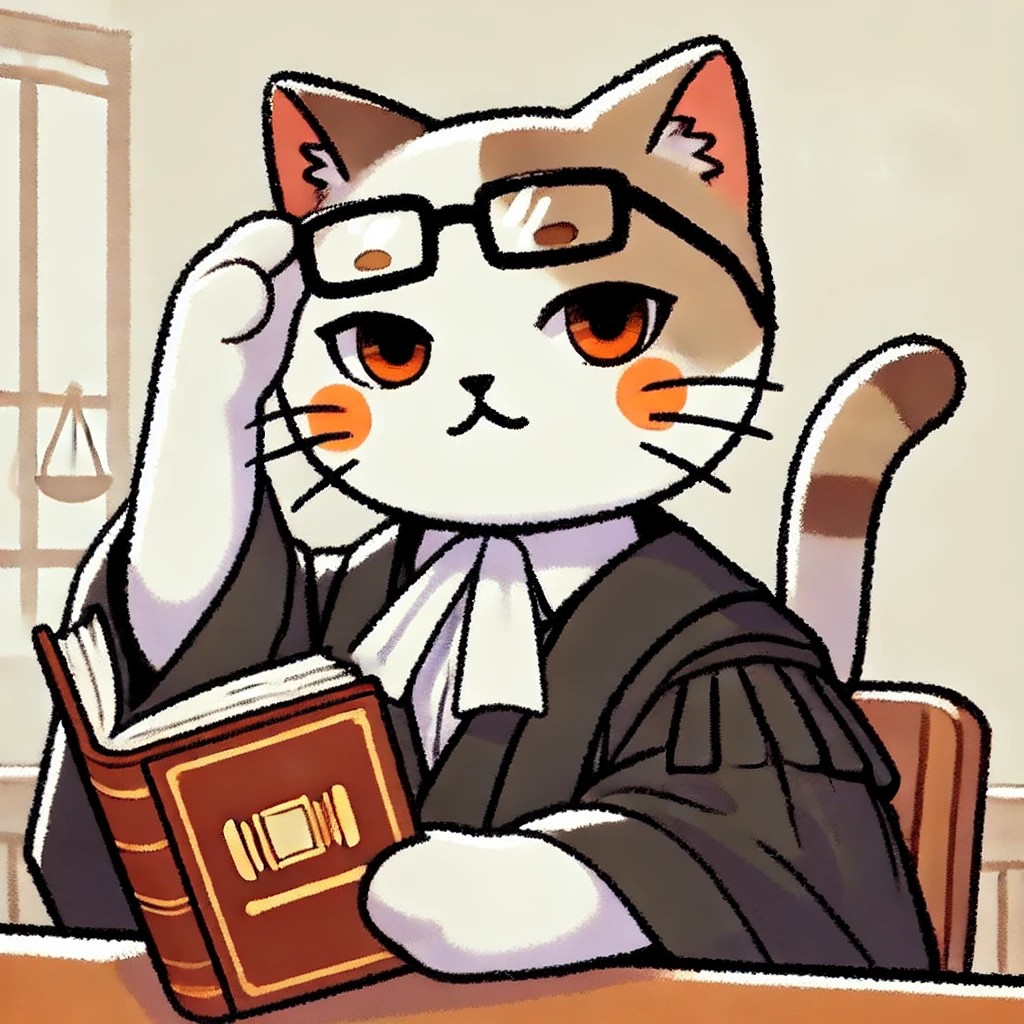
待期期間中の3日間は、会社から労基法の災害補償が支払われます。
所定労働時間内に労働災害が発生した場合、労働災害が起きた日が休業初日になります。残業で所定労働外に労働災害が発生した場合は、翌日が休業初日になります。
なお、休日や出勤停止等の懲戒処分を受けた日で、労働契約上の賃金請求権を有していない日でも休業補償給付は支給されます(最高裁昭和58年10月13日判決)。有給を消化した場合は、支給対象外です。
退職後の給付
労災保険の給付を受ける権利は、労働者が退職しても消滅しません(労災保険法12条の5第1項)。労働者が療養中に退職しても、上記の要件を満たせば引き続き休業補償給付を受けることができます。定年退職についても同様です。