労災保険の給付の内、遺族(補償)年金を取上げます。
遺族(補償)給付
遺族(補償)給付は、労働者が労働災害(労災事故、業務上疾病)や通勤災害で亡くなった場合に、被災労働者の遺族に対して支給されます(労災保険法16条)。
遺族補償給付には、以下の種類があります。
遺族補償給付の種類
①遺族補償年金
②遺族補償一時金
③遺族特別年金・遺族特別維持金
④遺族特別支給金
今回は、遺族補償年金について説明します。また、便宜上、遺族特別年金と遺族特別支給金(労災保険法29条1項・50条、労災保険特別支給金支給規則5条・9条)についても触れます。
遺族補償年金の支給要件
遺族補償年金を受給するには、次の要件をすべて満たす必要があります。
遺族補償年金の支給要件
(1)被災労働者が死亡した当時、その収入によって生計を維持していた→①生計維持関係
(2)被災労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であること→②受給資格・受給権者
(3)(2)の妻以外は年齢要件を満たしていること→③年齢要件
①生計維持関係
遺族が被災労働者と実際に同居していれば、基本的に生計維持関係が認められます。住民票等の書類上のことではなく、現実に同居していたか?が重要です。
被災労働者と別居していても、遺族と被災労働者との間で生活費・治療費などの経済的援助がなされていたり、定期的に訪問や連絡を取っていたという事情があれば、生計維持関係が認められることがあります。
生計維持関係には、被災労働者の収入で生計の一部を維持していれば足り、主として被災労働者の収入で生計を維持していたことまでは要求されません。
②受給資格・受給権者
配偶者には、実際に同居していて生計維持関係があれば、内縁関係も含みます。
被災労働者が法律上の配偶者と別に内縁の配偶者がいた重婚的内縁関係があった場合、重婚的内縁配偶者は原則として受給権者にはなりません。ただし、法律婚がすでに形骸化して実態を失い、実質的に法律上の離婚があったと同視できるような状況が認められれば、重婚的内縁配偶者が受給権者となります(東京地裁平成10年5月27日判決参照)。
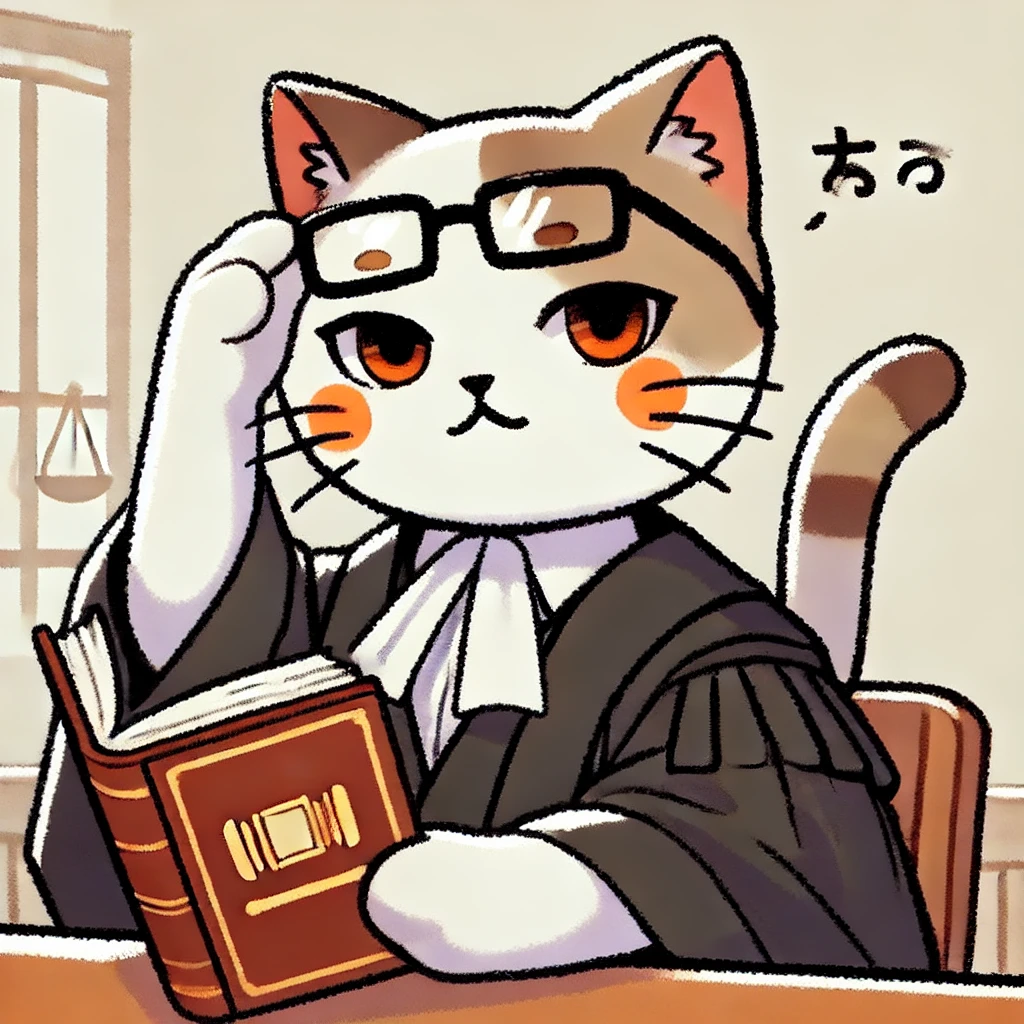
東京地裁平成10年5月27日判決の詳細は、以下の記事参照
受給資格者の優先順位
受給資格者が複数いる場合は、次の優先順位で実際の受給権者が決まります。第1順位の受給資格者がいる場合は、第2順位以下の受給資格者は、受給権者になりません。つまり、受給資格者の全員が受給権者になるわけではありません。
遺族補償年金の受給資格者の優先順位
①妻、60歳以上又は一定の障害の状態にある夫
②18歳までの間又は一定の障害の状態にある子
③60歳以上又は一定の障害の状態にある父母
④18歳までの間又は一定の障害の状態にある孫
⑤60歳以上又は一定の障害の状態にある祖父母
⑥60歳以上、18歳までの間又は一定の障害の状態にある兄弟姉妹
⑦55歳以上60歳未満の夫
⑧55歳以上60歳未満の父母
⑨55歳以上60歳未満の祖父母
⑩55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
転給
受給権者が亡くなったり、結婚したなどの理由で受給権者ではなくなった場合、受給資格者のうち、次の順位の遺族が繰り上がって受給権者になり、支給を受けることができます(労災保険法16条の4)。
③年齢要件
遺族補償年金の受給資格者・受給権者について、妻は年齢要件がありませんが、夫には上記のように年齢要件があります。これが、憲法14条(平等原則)や25条(生存権)に違反しないのか?という問題があります。
年齢要件は、民間労働者の労災保険ではなく、地方公務員の地公災・国家公務員の国公災にも存在します。地公災で年齢要件を争った事件で最高裁判決が出ています。一審は、原告の請求を認めました(大阪地裁平成25年11月25日判決)。控訴審は、原告の請求を認めませんでした(大阪高裁平成27年6月19日判決)。そして、最高裁も原告の請求を認めませんでした(最高裁平成29年3月21日判決)。
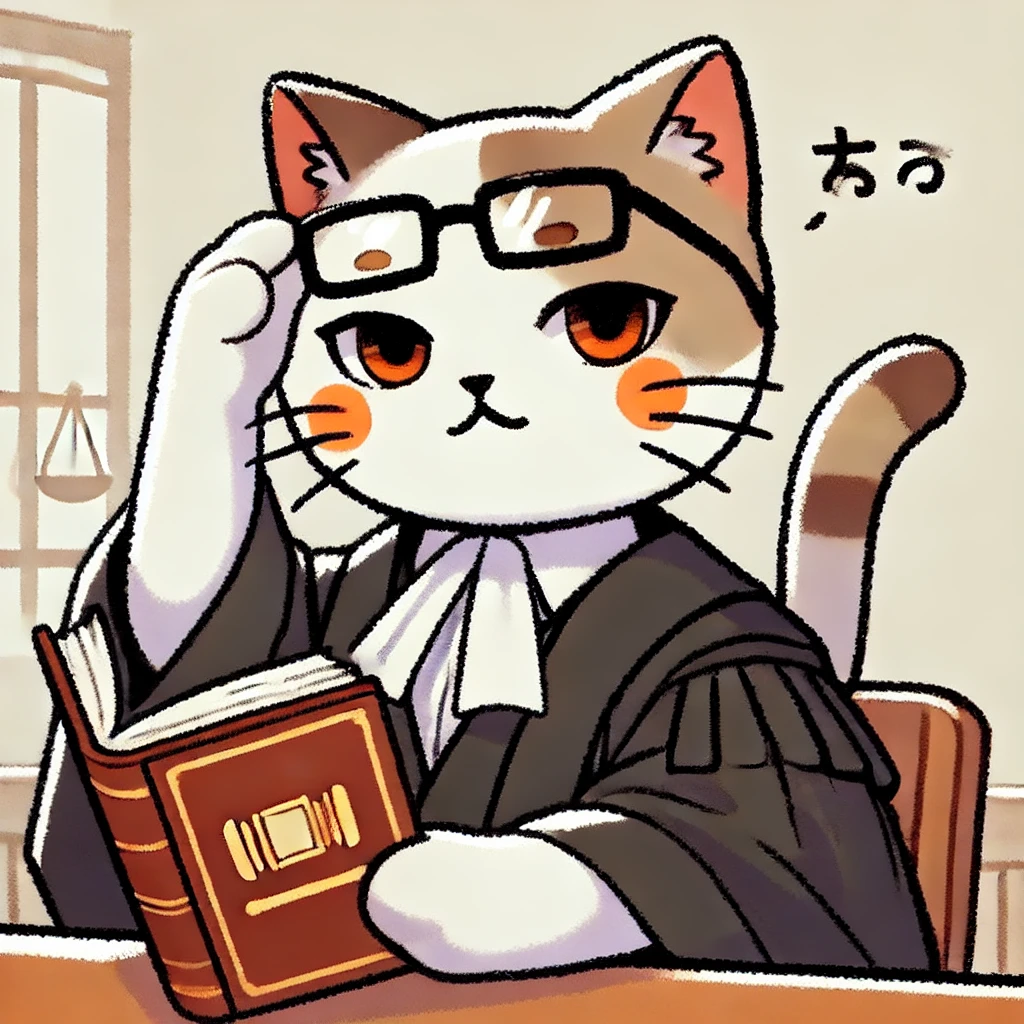
最高裁平成29年3月21日判決の詳細は、以下の記事参照
若年停止
受給権者が夫、父母、祖父母、兄弟姉妹の場合、被災労働者が死亡した時点で60歳未満であれば(上記⑦~⑩)、60歳になるまで年金の支給が停止されます。これを若年停止といいます。
受給権者に労災保険の後遺障害5級以上に該当する障害がある場合は、一定の障害がある場合に該当し、年金の支給は停止されません(労災保険規則15条)。
支給内容
下記のように遺族の人数に応じて年金が支給されます。遺族の人数にかかわらず、一時金として特別支給金300万円が支給されます。
| 遺族の人数 | 遺族補償年金 | 遺族特別年金 |
| 1人 | 給付基礎日額153日分 | 算定基礎日額の153日分 |
| 2人 | 給付基礎日額201日分 | 算定基礎日額201日分 |
| 3人 | 給付基礎日額223日分 | 算定基礎日額223日分 |
| 4人以上 | 給付基礎日額245日分 | 算定基礎日額245日分 |
なお、遺族の人数が1人で、受給権者が55歳以上の妻又は一定の障害の状態にある場合は175日分が支給されます。