安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求において、労働者の過失を認め、過失相殺を行った裁判例を紹介します。
グルメ杵屋事件(大阪地裁平成21年12月21日判決)
飲食店の店長が急性心筋梗塞を発症し、死亡した事案です。
裁判所は、使用者の安全配慮義務違反を認めました。しかし、店長として業務軽減を使用者に求める措置を採らず、自らの健康保持に対する配慮も不十分な点があったとして、2割の過失相殺を行いました。
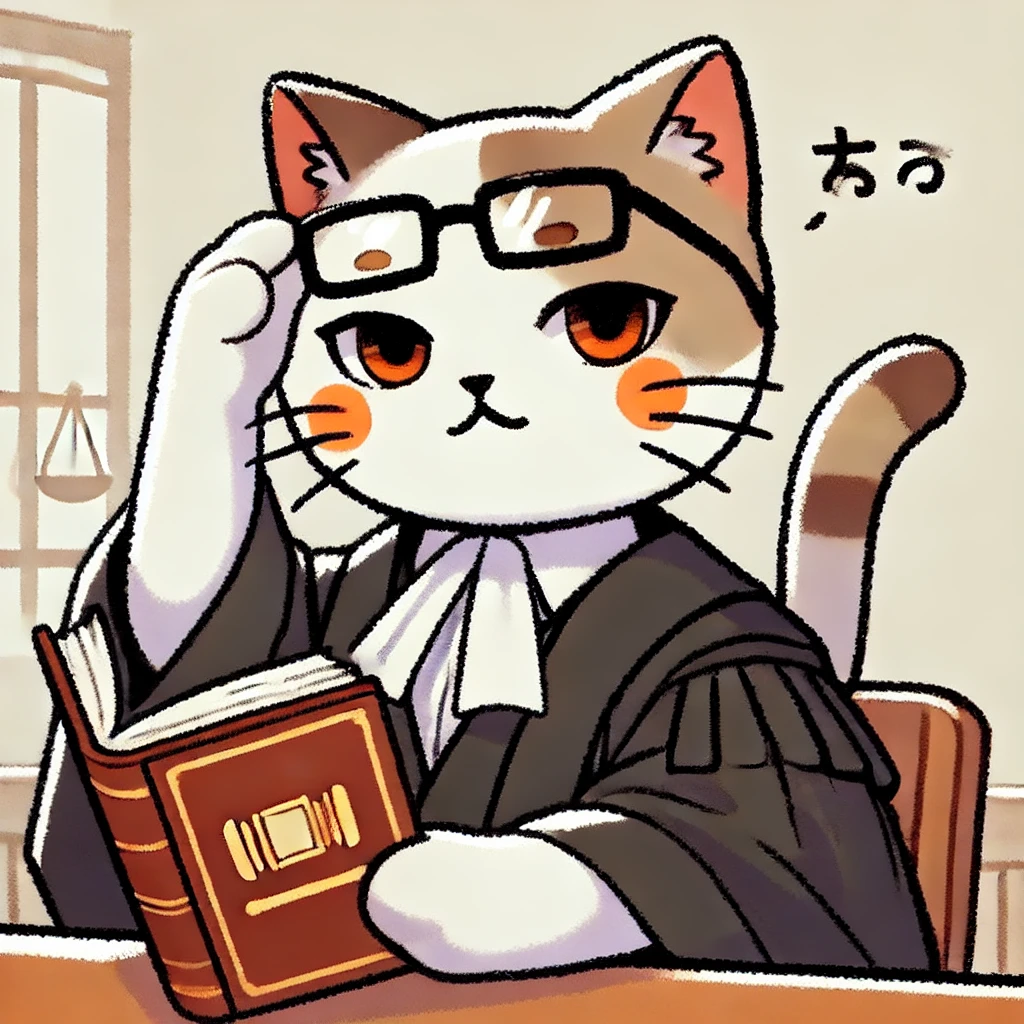
以下の「労災の損害賠償と従業員の自己保健義務」も参照
この判決を前提とすると、会社内で一定の地位にある労働者は、長時間労働等の是正を使用者に求めることが、その職務権限・職責である場合は、それらの職責を果たさなければ、過失相殺される可能性があります。
事案の概要
亡Dは、平成9年3月に大学を卒業後、同年4月1日に被告に入社し、入社とともに平成11年8月まではM店で勤務し、同年9月からは被告でいうところの監督職となるとともに、同月からN館、平成12年10月からO店、同年12月からはP店等を歴任し、平成14年8月1日に本件店舗の店長となった。
店長の業務は、店舗全体の確認、パートらへの指示・指導、年間・月間・日割予算の作成、損益計算書の作成、基本シフトの作成、原材料の仕入れ、仕込み・廃棄処分・清掃・整備の指示と確認、接客の先頭に立ち苦情処理を行うこと、伝票整理・日報の記載・レジ精算のチェック、月に一度の本社での店長会議に出席すること、月に一度の棚卸しなどである。被告らにおいては、店長として心がけるべき諸事項を記した「店長職務基準」等を内容とする本件店長マニュアルが定められている。
亡Dは、原告らと同居していたころは、おおむね、午前9時前後に自宅を出て翌午前1時から午前2時の間に帰宅していた。亡Dは、公休日はとっていたが、ほとんど自宅で過ごしており、原告Aに背中等のマッサージをするようにたびたび頼むなどしていた。
原告らは、平成11年ころから亡Dの顔色が良くなく、以前に比べてやせてほおが落ちているように感じたため、これを心配して亡Dに対し、過労死も多くある時代であるから、健康は自分で十分に注意するようになどと忠告していた。
平成14年10月ころの本件店舗の正社員は、G、亡D、Q及び料理長のRの4名であり、Gが支配人、亡Dが店長であり、Gが店舗を統轄していた。その後、Gが平成15年1月11日ころから被告らが経営するSのラーメン店での勤務を始め、同年2月1日付けで同店へ異動したため、亡Dが、名実ともに本件店舗を統轄することになったが、正社員は一旦3名に減った。その後、本件店舗では、正社員で、CのO店で店長をしていたHが平成15年3月1日から同年4月末までは応援として勤務し、亡Dとともに店長を務めたほか、Iも勤務した。
亡Dは、Gが他店舗に移った後は、ホールと厨房の皿洗い等の両方の業務を行うようになり、勤務時間も長くなって、休日もほとんど出勤するようになった。また、亡Dは、前記の店長業務に加え、材料の発注等も自ら行い、月に一度の棚卸しも一人で行っていた。なお、亡Dは、まじめで几帳面で、人から言われたら断れないような性格であった。
亡Dは、ホールで接客をする接客部門を担当するパートらとの人間関係には問題がなかったが、料理長や厨房部門を担当するパートらとの関係は良好ではなく、厨房部門のパートらは、料理長の意向を受け、亡Dの指示に従わないことがあった。
これは、本件店舗の経営が厳しかったため、店長である亡Dが人件費削減等のために厨房の皿洗い要員を廃止して厨房部門に割り振ろうとしたこと、パートらの希望する勤務制を組めなかったこと、厨房の人数を増やしてほしいとの料理長からの要望に応じられなかったこと等が原因であった。
そのため、亡Dが、厨房部門のパートらに対し、細かな清掃や全員で皿洗いをすること等を指示しても聞いてもらえず、皿洗いは、亡Dやホール部門の従業員が行っていた。なお、食器は、自動食器洗浄機を使用して洗うが、その前に大きな汚れを取る等のため、一旦手洗いをする必要があった。
本件店舗では、午後2時から午後6時が、基本的にはアイドルタイムであった。しかしながら、亡Dは、この時間にもパートらとともに午前中から残っている食器の洗い物をしたり、午後の材料を倉庫から持ってきて整えたり、ホールの清掃をする他、休憩中の料理長に代わって調理を行うこともあった。そのため、亡Dは、アイドルタイム中に店長がすべき事務作業ができないときがあった。亡Dは、朝従業員が出勤したときに、本件店舗のソファーで寝ていることが2週間に一、二回程度あり、本件発症の1か月前くらいには、アイドルタイムに月に一、二回仮眠をとっていた。
亡Dは、栄養飲料を飲むことが多く、本件発症の1か月前ころには、パートのLに対し、笑いながらも、疲れた等とよく言っていた。また、亡Dは、監査と研修前には、これらが重なっていることが一番しんどいとも言っていた。亡Dは、本件発症の前日である平成15年4月21日は、午前2時21分に本件店舗に出勤し、業務をしたのち、閉店後の翌22日午前0時15分から午前2時30分まで、U及びHとともに店長3名で自主的なミーティングを実施していた。Uらは、ミーティング終了後に帰宅したが、亡Dは、店内に止まった。
亡Dは、午前11時ころから午後11時ころまでの本件店舗の営業時間中は、アイドルタイムの間も含めて、基本的には業務を行っていた。
本件店舗では、亡Dが、従業員の中で最後まで在店しており、セキュリティ装置をセットして帰宅していた。亡Dは、営業時間終了後、皿洗いや清掃、店長業務等の事務作業、研修や店長会議前にはその準備、監査前には清掃等を行っていたものと推認されるから、同人は、営業時間終了後の在店時間についても、基本的には業務を行っていた。
亡Dは、平成15年4月22日午前7時ころ、本件店舗において、冠動脈硬化症による急性心筋梗塞により死亡した。
裁判所の判断
前述のとおり、裁判所は、使用者の安全配慮義務違反を認めた上で、被害者の過失を2割とする過失相殺を行いました。
亡Dの労働時間は著しく長時間であると認められる。そして、その業務内容も、特にGの転出後は、以前よりも業務量が増した上、本件店舗の経営が厳しかったことなどから、店長として人員削減等の経営立て直しのための対策を講ずる必要があって、精神的負荷のかかるものであった。また、本件店舗では、上記対策の影響により、厨房部門の従業員らとの関係が悪化し、同従業員らが指示に従わないため、従業員らとの適切な業務分担もできなかったものである。さらに、亡Dは、日々の業務に加え、店長として監査、店長会議、研修等にも対応をする必要があった。
以上に照らせば、亡Dの業務は、継続的な長時間労働である上、その内容も身体的精神的負荷のかかるものであったと認められるから、過重であったと認められる。
以上に照らせば、亡Dは、本件店舗の店長として過重な労働に従事し、十分な休憩や休日も取れなかったため、冠動脈が自然経過を超えて著しく硬化した結果、急性心筋梗塞が発症し、本件死亡に至ったものであるから、亡Dの業務と本件発症・死亡との間には、相当因果関係があると認められる。
被告らは、亡Dを長時間の時間外労働や精神的負荷のかかる業務に従事させたため、同人は、これによって疲労を蓄積し、本件発症をして死亡するに至った。被告らは、客観的に労働時間の実態を把握できるこれらの方策を採らず、亡Dに対し、自己申告による出勤表を提出させていたのみである。そして、本件全証拠によっても、被告らが上記出勤表の内容が亡Dの実際の労働時間と合致しているかについての実態調査等を行った形跡は認められない。
以上に照らせば、被告らの亡Dに対する労働管理は、まことに不十分なものであり、被告らが、亡Dの労働時間を適正に管理する義務を怠っていたことは明らかである。被告らは、亡Dの労働時間を適切に管理せず、同人の労働時間、休憩時間、休日等を適正に確保することなく、長時間労働に従事させたものであるから、安全配慮義務違反が認められる。そして、被告らの上記安全配慮義務違反と本件死亡との間には、因果関係が認められる。
したがって、被告らは、本件死亡について安全配慮義務違反の債務不履行責任及び不法行為責任を負うと認められる。
亡Dは、店長として、本件店舗の従業員を指示監督する立場にあったのであるから、たとえ、店長として自ら率先して業務を行うことが求められる局面がある。他方、管理者としての指導力を発揮し、自己の負担を含め、従業員間の仕事の分担の適正さを図り、店舗全体としての業務の効率化を図ることも、その権限及び責務に照らし、求められていた。したがって、亡Dとしても、必ずしも指導や業務命令が徹底できなかった厨房部門を含め、店長として本件店舗における仕事量の配分や従業員に対する指示の方法ないし内容に意を用いて、自らの業務量を適正なものとし、休息や休日を十分にとって疲労の回復に努めるべきであり、本件店舗の経営状況・人間関係、業務内容等を勘案しても、当時の本件店舗がこれを行うことを期待できない状態にあったとはいえない。
これに加え、亡Dが適宜の機会をとらえ、被告らに対し、本件店舗の懸案事項と考えられるもの、すなわち、本件店舗の経営状況、従業員の不足・勤務状況及び自己の業務の状況等を申告するなどして、亡Dが被告らに対し、業務軽減のための措置を採るよう求めることもまた、店長の任務の内であり、これが不可能であったともいえない。
それにもかかわらず、亡Dは、穏やかな性格で、仕事を自ら引受けるような面があったにせよ、結果として上記措置を採らず、すべて自己の負担に帰していたのであるから、店長としての業務遂行に当たって不十分な面があるとともに、自らの健康保持に対する配慮も十分ではなかったといわざるを得ない。
以上に照らせば、亡Dには、本件死亡について一定の過失があったというべきであり、その割合は、2割と認めるのが相当である。