労災保険の給付の内、障害(補償)給付を取上げます。
障害(補償)給付
労災による傷病で治療を受けてきた被災労働者が症状固定(労災では、治ゆといいます)の状態に至り、後遺障害が残存した場合、障害の程度に応じて障害(補償)年金、障害(補償)一時金、障害特別年金、障害特別一時金、障害特別支給金が支給されます(労災保険法15条1項・特別支給金支給規則4条・7条)。
後遺障害の等級認定
後遺障害の等級認定は、被災労働者の障害を障害等級表にあてはめて決定します。あてはめに当たっては、障害等級認定基準に基づいて行われます。
交通事故の自賠責保険の後遺障害の認定は、醜状障害を除いて書面審査で行われます。労災保険は、労基署で被災労働者と面談の上、労災医員の意見を聴いて認定します。
大阪労働局管内の労基署では、面談は労災医員と行われます(地方では、労災医員との面談がないこともあります)。医師が後遺障害の認定に関わっているからなのか、自賠責保険と比べて労災保険は、後遺障害が認められやすく、自賠責よりも上位の等級が認められることもあります。
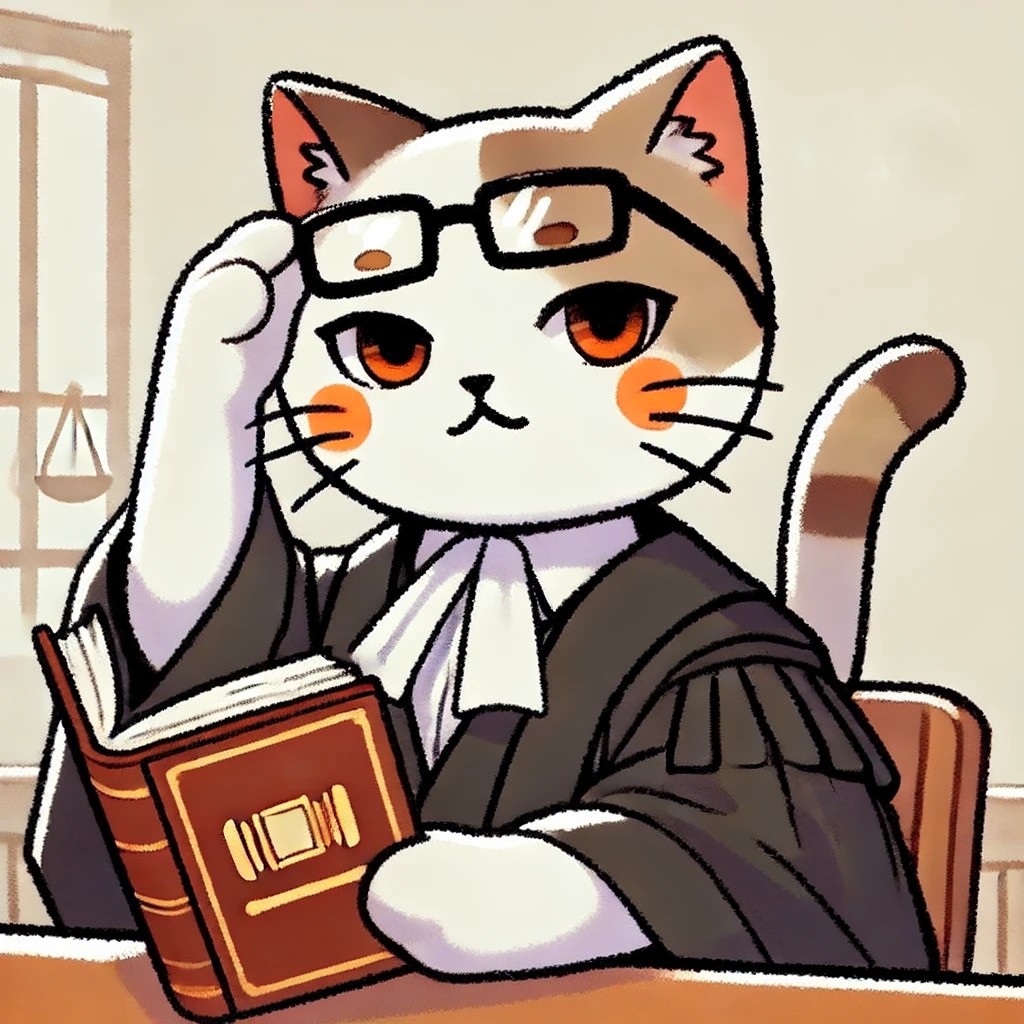
以下の「労災の後遺障害の認定」も参照
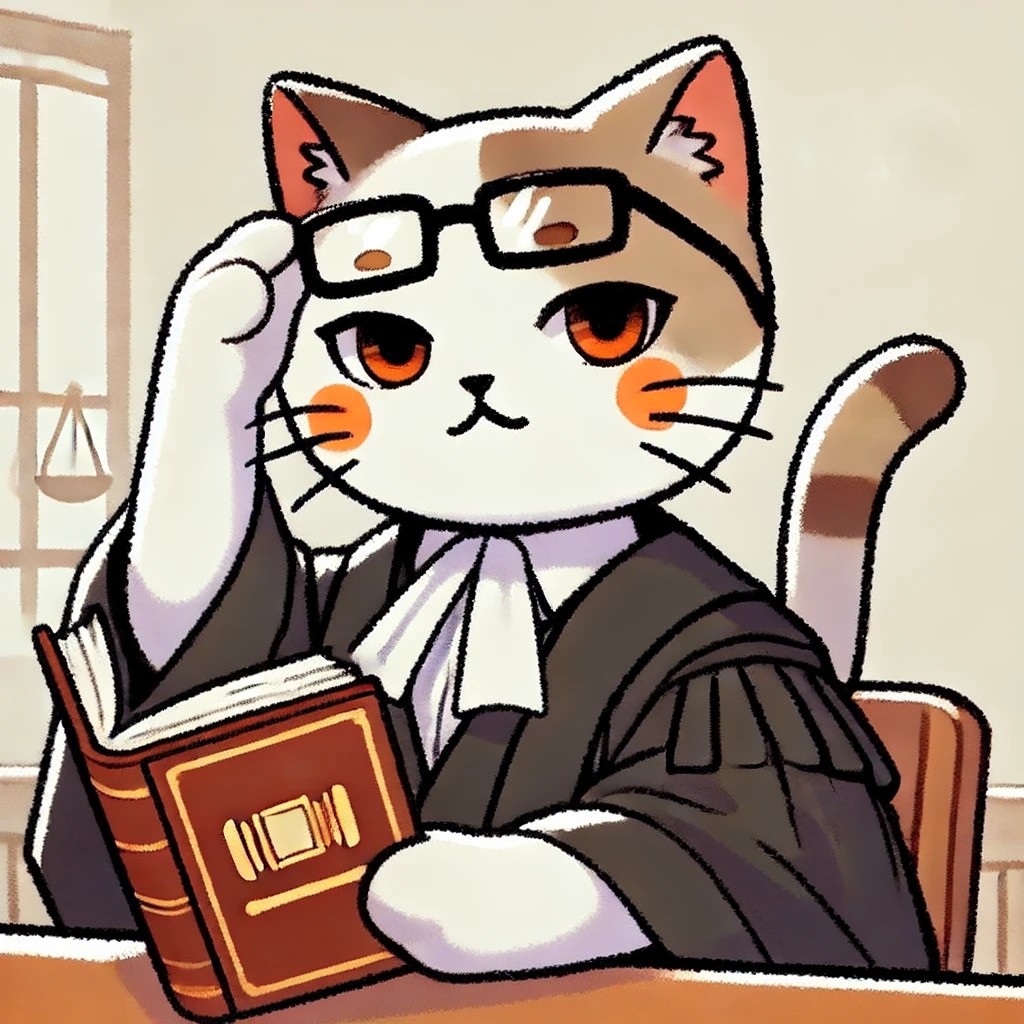
後遺障害の認定基準については、法律事務所エソラの交通事故のWebサイトに適宜、解説記事を書いていますので、そちらをご参照ください。
障害(補償)給付の給付内容
| 障害等級 | 障害補償給付 | 障害特別支給金 | 障害特別年金 | 障害特別一時金 |
| 1級 | 給付基礎日額313日分 | 342万円 | 算定基礎日額313日分 | なし |
| 2級 | 給付基礎日額277日分 | 320万円 | 算定基礎日額277日分 | |
| 3級 | 給付基礎日額245日分 | 300万円 | 算定基礎日額245日分 | |
| 4級 | 給付基礎日額213日分 | 264万円 | 算定基礎日額213日分 | |
| 5級 | 給付基礎日額184日分 | 225万円 | 算定基礎日額184日分 | |
| 6級 | 給付基礎日額156日分 | 192万円 | 算定基礎日額156日分 | |
| 7級 | 給付基礎日額131日分 | 159万円 | 算定基礎日額131日分 | |
| 8級 | 給付基礎日額503日分 | 65万円 | なし | 算定基礎日額503日分 |
| 9級 | 給付基礎日額391日分 | 50万円 | 算定基礎日額391日分 | |
| 10級 | 給付基礎日額302日分 | 39万円 | 算定基礎日額302日分 | |
| 11級 | 給付基礎日額223日分 | 29万円 | 算定基礎日額223日分 | |
| 12級 | 給付基礎日額156日分 | 20万円 | 算定基礎日額156日分 | |
| 13級 | 給付基礎日額101日分 | 14万円 | 算定基礎日額101日分 | |
| 14級 | 給付基礎日額56日分 | 8万円 | 算定基礎日額56日分 |
障害(補償)給付等の給付内容は、上記の表のとおりです。1級~7級までは年金として支給されます。8級以下は、一時金が支給されます。