うつ病・過労自殺といった精神障害の労災認定における心理的負荷の強度の評価方法を取上げます。
精神障害の労災認定基準
精神障害(過労自殺を含む)の労災認定基準では、「業務による強い心理的負荷」があったか?を審査します。
特別な出来事がある場合は、それだけで、業務による強い心理的負荷があったと認定されます。
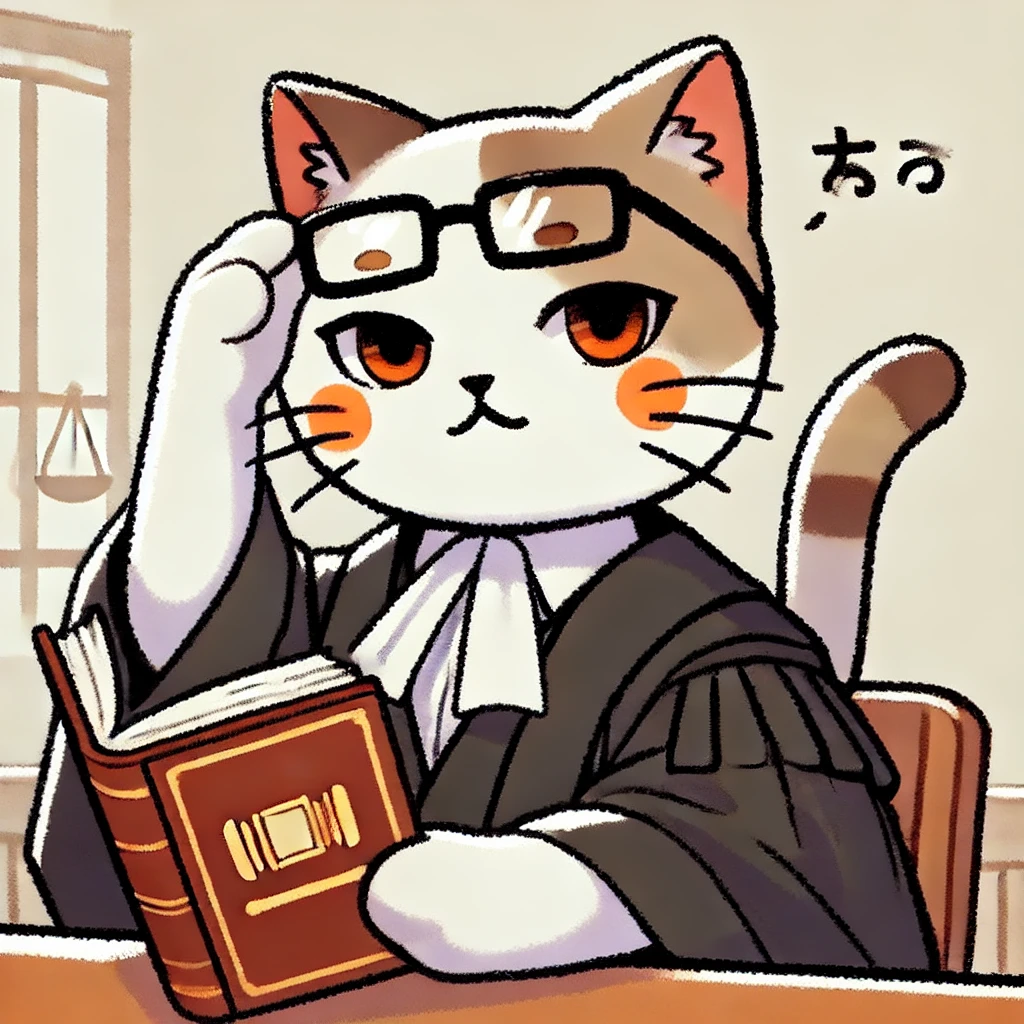
特別な出来事の詳細は、以下の記事参照
それでは、特別な出来事がない場合は、どのように認定するのでしょうか?
業務による心理的負荷評価表
精神障害の労災認定基準は、業務による心理的負荷評価表というのを作成しています。精神障害の発病前6か月間に認められた業務による出来事が、心理的負荷評価表の具体的出来事のどれに当たるか?を判断します。しかし、心理的負荷評価表の具体的出来事に、完全に一致することは少ないです。合致しない場合は、近い具体的出来事に当てはめます。
「業務による心理的負荷評価表」は、心理的負荷の強度を「強」、「中」、「弱」の3つに区分しています。
「強」、「中」、「弱」の評価は、具体的な出来事と出来事後の状況を加味して行います。そして、発病前6か月間の業務による出来事について、心理的負荷の強度が「強」であれば、業務による強い心理的負荷があったと判断されます。
平均的な心理的負荷の強度
心理的負荷評価表は、具体的出来事ごとに、その平均的な心理的負荷の強度を定めています。心理的負荷の強度は、「Ⅲ」・「Ⅱ」・「Ⅰ」の3段階で、「Ⅲ」が一番強く、「Ⅰ」が一番弱いです。
心理的負荷の強度と平均的な心理的負荷の強度
「Ⅲ」・「Ⅱ」・「Ⅰ」は、上記のとおり、平均的な心理的負荷の強度を定めたものです。労災認定に当たっては、労働者の主張する出来事とその出来事の前後の状況を加味した心理的負荷の強度が「強」・「中」・「弱」か?を評価します。
平均的な心理的負荷の強度が「Ⅲ」の出来事は、通常想定される出来事後の事情を加味すると、心理的負荷の強度が「強」となることが想定されています。「Ⅱ」と「中」、「Ⅰ」と「弱」の関係も同様です。
具体例
具体的な例を少し挙げておきます。
| 具体的出来事 | 平均的心理的負荷の強度 | 「弱」「中」「強」の具体例 |
| 退職を強要された | Ⅲ | 退職の意思がないことを表明しているにもかかわらず、執拗に退職を求められた→「強」 |
| 上司とのトラブルがあった | Ⅱ | 上司から業務指導の範囲内である強い指導、叱責を受けた→「中」 |
| 1か月に80時間以上の時間外労働を行った | Ⅱ | 1か月に80時間以上の時間外労働を行った→「中」 |
具体的出来事ごとの心理的負荷の総合評価
実際に生じた出来事を心理手負荷評価表の具体的出来事に当てはめ、認定した出来事や出来事後の状況について事実関係が合致する場合は、その強度で心理的負荷の強度を認定します。
心理的負荷評価表で列挙されている具体例は例示です。したがって、その他の出来事が、心理的負荷の強度「強」と判断されないわけでは決してありません。
実際の事実関係が具体的出来事に合致しない場合は、「心理的負荷の総合評価の視点」や「総合評価における共通事項」に基づき、具体例を参考にしながら、事案ごとに心理的負荷の強度を認定します。
総合評価の留意点
①出来事それ自体と、②出来事の継続性、事後対応の状況、職場環境の変化等の出来事後の状況の両者を十分に検討します。
心理的負荷評価表で例示されていないものも、出来事に伴い発生したと認められる状況、出来事が発生するに至った経緯等も含め総合的に考慮し、出来事の心理的負荷を評価します。
職場の支援・協力が欠如した状況や仕事の裁量が欠如した状況であることは、総合評価を強める要素になり得ます。