精神障害の労災認定は、業務による心理的負荷を業務による心理的負荷評価表の具体的出来事に当てはめて評価をします(心理的負荷の評価の仕方参照)。具体的な出来事の類型の④役割・地位の変化を取上げます。
役割・地位の変化
精神障害の労災認定基準は、心理的負荷表の具体的な出来事の類型として役割・地位の変化を挙げています。さらに、認定基準は、以下のように細分類しています。
退職の強要
平均的な心理的負荷の強度はⅢとされています。
解雇又は退職の結果のみで評価をしません。解雇又は退職強要の経過、強要の程度、職場の人間関係等により心理的負荷の総合評価を行います。なお、「解雇又は退職強要」には、雇止めも含むとされています。
退職勧奨が行われたが、その方法、頻度等から強要といえない場合の心理的負荷の強度は、「弱」又は「中」となります。
心理的負荷の強度が「強」となる例
心理的負荷が「強」となる例として、以下の3つが挙げられています。
心理的負荷の強度が「強」になる例
(1)退職の意思がないことを表明しているにもかかわらず、執拗に退職を求められた。
(2)恐怖感を抱かせる方法を用いて退職勧奨された。
(3)突然解雇通告を受け、何ら理由が説明されることなく、説明を求めても応じられず、撤回されることもなかった。
配置転換があった
平均的な心理的負荷の強度はⅡとされています。職種・職務の変化の程度、配置転換の理由・経過等、業務の困難性、能力・経験と業務内容のギャップ等、その後の業務内容、業務量の程度、職場の人間関係等により心理的負荷の総合評価を行います。
ここでいう配置転換とは、所属部署・勤務場所の変更を意味します。
心理的負荷の強度が「強」となる例
心理的負荷の強度が「強」になる例として、以下の3つを挙げています。
心理的負荷の強度が「強」になる例
(1)過去に経験した業務と全く異なる業務に従事することになったため、配置転換後の業務に多大な労力を費やした。
(2)配置転換後の地位が過去の経験からみて異例なほど重い責任が課されるものであった。
(3)明らかな降格であって配置転換としては異例なものであり、職場内で孤立した状況になった。
転勤した
転勤とは、勤務場所の変更で転居を伴うものです。転居を伴わないものは、配置転換です。
平均的な心理的負荷の強度はⅡとされています。職種・職務の変化の程度、転勤の理由・経過等、単身赴任の有無、海外の治安状況等、業務の困難性、能力・経験と業務内容のギャップ等、その後の業務内容、業務量の程度、職場の人間関係等により心理的負荷の総合評価を行います。
心理的負荷の強度が「強」となる例
転勤先が初めて赴任する海外で、現地の職員との会話が不能、治安状況が不安といった事情から転勤後の業務遂行に著しい困難を伴った場合は、心理的負荷の強度が「強」とされています。
複数名で担当していた業務を一人で担当するようになった
平均的な心理的負荷の強度はⅡとされています。業務の変化の程度、その後の業務内容、業務量の程度、職場の人間関係等により心理的負荷の総合評価を行います。
なお、業務を1人で担当することに伴う、仕事量(労働時間)の変化(増加)は、「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事」として評価します。
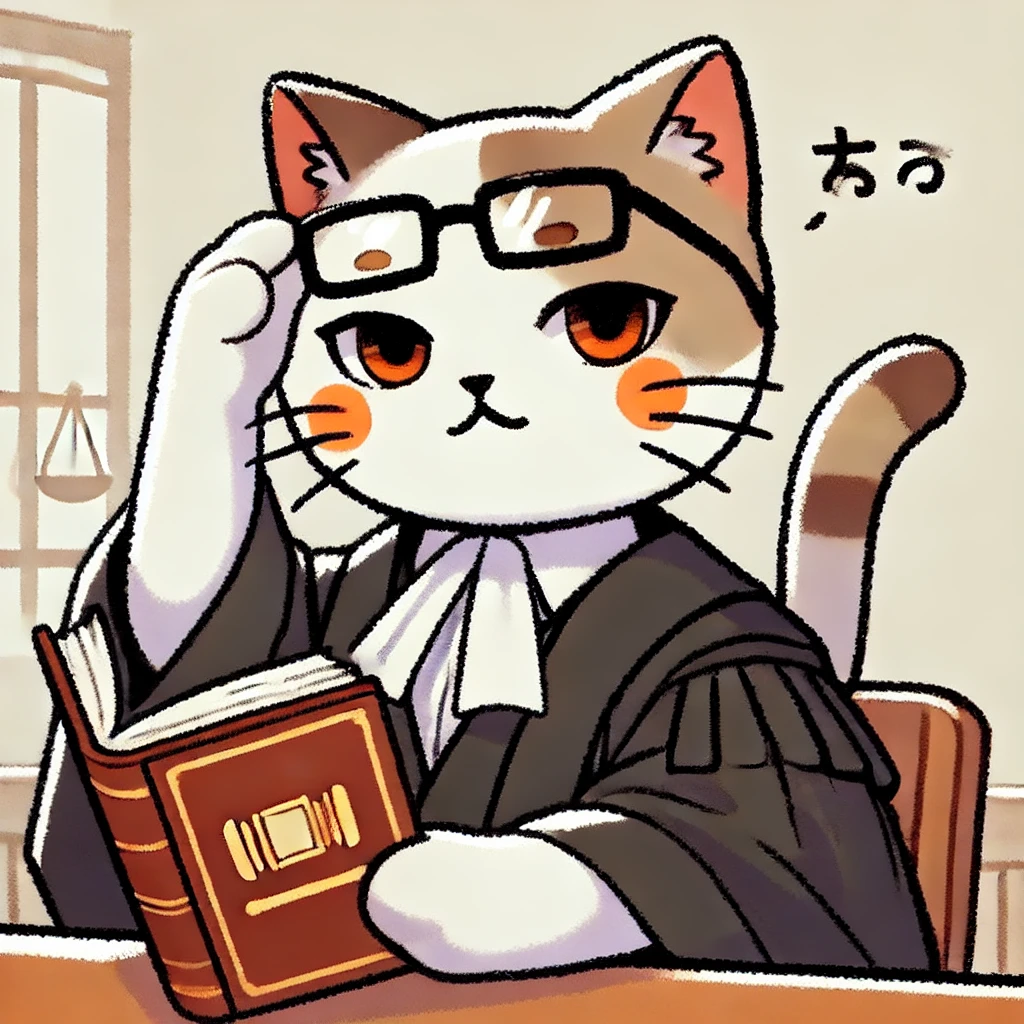
「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事」については、以下の記事参照
心理的負荷の強度が「強」になる例
業務を一人で担当するようになったため、業務量が著しく増加し時間外労働が大幅に増えるなどの状況になり、かつ、必要な休憩・休日も取れない等常時緊張を強いられるような状態になった場合は、心理的負荷の強度が「強」とされます。
非正規社員であるとの理由等により、仕事上の差別、不利益取扱を受けた
平均的な心理的負荷の強度はⅡとされています。差別・不利益取扱いの理由・経過・内容・程度、職場の人間関係等により心理的負荷の総合評価を行います。
心理的負荷の強度が「強」になる例
仕事上の差別、不利益取扱いの程度が著しく大きく、人格を否定するようなものであって、かつ、これが継続した場合は、心理的負荷の強度は「強」とされます。