緊急業務中の災害を労災と認定した裁判例を紹介します。
名古屋地裁平成20年9月16日判決
緊急業務中の災害によって、労働者が死亡した事案です。労災と認められるかどうか?が争われました。
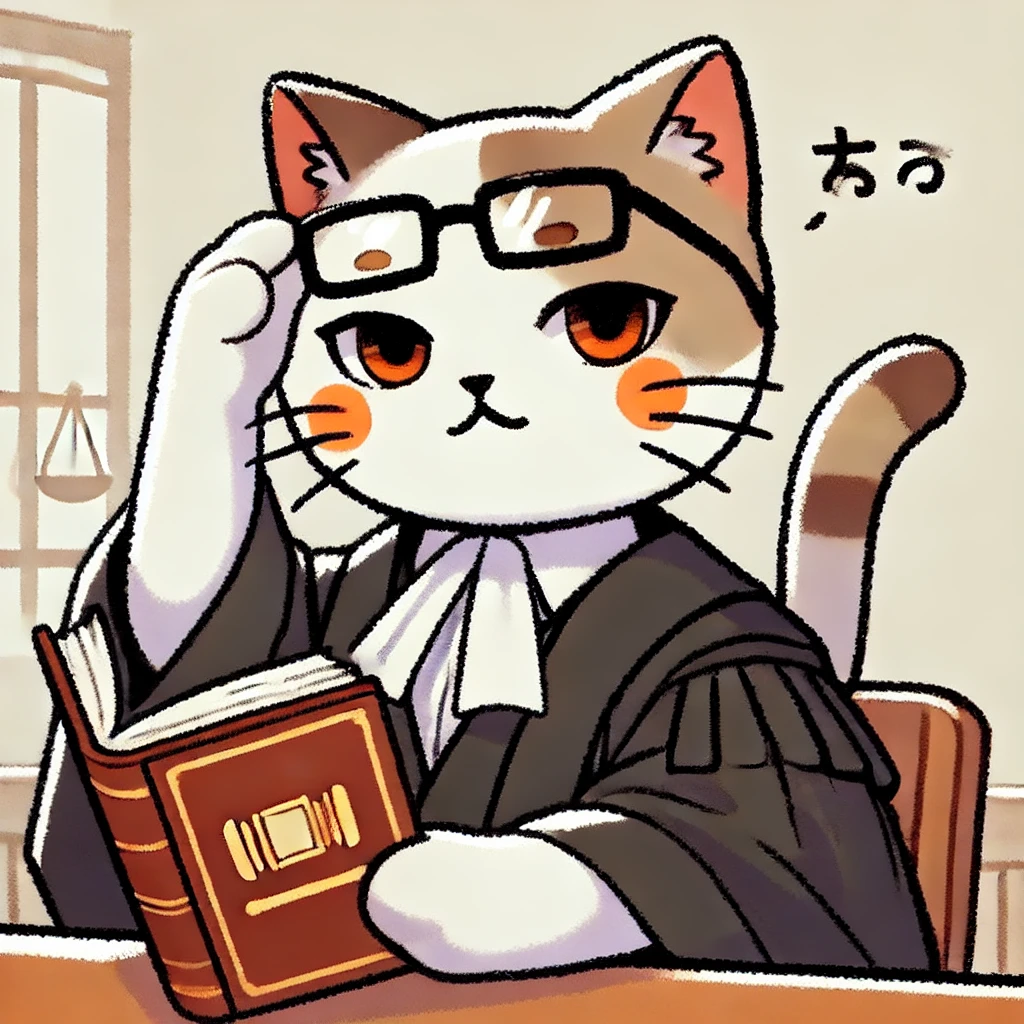
以下の「緊急業務中の災害と労災」も参照
事案の概要
被災者Kは、午前1時ころ、会社の業務としてトレーラーに荷物を積載して、国道21号線を走行中、岐阜県大垣市内で、軽自動車が横転している現場に遭遇し、同車から脱出した者から事故車内に閉じ込められている同乗者の救助を求められた。
このため、被災者Kは事故車の前方にトレーラーを停めて、後続車の男性と協力して事故車内に閉じ込められていた2名の女性を救出した。
その後、上記男性と事故車を起こそうとしていた際、後方から走行してきたY運転の普通乗用車が事故車に衝突し、被災者Kは前方に押し出された事故車とトレーラーの間に挟まれて負傷し、大垣市民病院に搬送されたものの、同日午前2時35分、頭蓋骨骨折により死亡した。
被災者Kの遺族であり、かつ、被災者Kの葬祭を行った原告は、平成10年9月11日、本件事故は労働災害に当たるとして、半田労働基準監督署長に対し、労災保険法に基づき、遺族補償年金給付及び葬祭料の給付を請求した。
半田労働基準監督署長は、上記請求に対し、平成10年10月16日付けで遺族補償年金給付及び葬祭料の給付を支給しない本件処分をし、同月23日、原告に通知した。不支給決定通知書には、不支給理由として、「業務上の傷病とは認められない。」という記載がある。その後、審査請求及び再審査請求ともに棄却された。
裁判所の判断
裁判所は、業務遂行性・業務起因性ともに肯定し、労災と認定しました。
まず、業務遂行性について判断するに、確かに、事故車の横転は被災者Kの運送業務及び同人運転車両の運行に由来するものではなく、また、これを見過ごして通過することも不可能ではなかったことが認められ、本件救助行為等は、一見、被災者Kの運送業務からは逸脱した行為に映る。
しかしながら、事故車の横転は、被災者Kが会社の業務としてトレーラーを運転していた道中に見掛けたものであり、同人の運行コースが外れていた様子もなく、まさに業務の最中に遭遇したものということができる。そして、被災者Kが目の当たりにした光景は、深夜、軽自動車が第2車線を塞ぐようにして横転している状況であり、しかも、女性から横転車両内に閉じ込められている同乗者の救出を求められたというのであるから、これを放置していては、人の生命に関わりかねない、一刻を争う重大な事故である可能性を疑うべき状況にあったといえ、このような事態に至って、少々時間をかけても業務に支障のない被災者Kが、本件救助行為等に着手したのも無理からぬものがある。かえって、救助を無碍に断り、通り過ぎれば、本人としても良心の呵責を覚え、社会的にも道徳的非難を浴びかねないところである。
運送事業者の運行管理者の講習用テキストにおいても、事故があった場合に他の運転者に協力を呼びかけ、運転者同士が相互協力し合うことを想定した記述が認められ、交通事故において救助等を求められた場合に、可能な限り協力することは自動車運転者として奨励される行為であったということができ、本件救助行為等は、自動車運転を行う労働者として、通常予想される範疇の行動と言い得るものである。
会社としても、上記のような状況下で、これを放置して運送業務を継続することが望ましいと認識したとは到底考え難い。現に、本件事故後に、会社において行われた事故対策の検討においても、被災者Kの車両の停止位置が問題とされたことはあったが、本件救助行為等を行うこと自体が問題視された様子はなく、また、会社のN営業所長も、本件事故後、被災者Kの死亡について労災認定がなされることを希望し、さらに、会社として、被災者Kの社葬を遺族に打診していたというのであるから、会社が被災者Kの執った行動を支持していたことは明白である。
以上の諸点に照らせば、事故車の同乗者から救助を要請されて行った本件救出行為等は、長距離の自動車運転業務に従事する労働者が、業務を行う上で当然なすことが予想される行為であり、本件事故は業務遂行中の災害と認めるのが相当である。
次いで、業務起因性について判断するに、被災者Kの業務は長距離の自動車運転であり、仕事柄、業務中に交通事故に遭遇することも想定されるところであり、かつ、事故の処理中に、後続車の追突事故に巻き込まれる可能性も予想されるものであるから(運送事業者の運行管理者の講習用テキストにおいても、事故処理中に他の車が突っ込んでくる可能性があることを前提とした記述がある。)、このような事故に遭遇する危険性は、自動車運転を内容とする業務に内在するものといえる。したがって、運送業務途中の事故処理中に後続車のY運転車両が追突してきたという本件事故も、被災者Kの業務に内在する危険性が現実化したものということができ、被災者Kの業務と相当因果関係があると認めるのが相当である。
以上によれば、本件事故による被災者Kの死亡は業務上の災害と認められる。