精神障害の労災認定は、心理的負荷の強度を評価しています。心理的負荷の強度を評価する際に、同種労働者の平均を基準に評価します。同種労働者の平均とは、どういう意味なのでしょうか?
業務による心理的負荷の強度を誰を基準に判断するのか?
精神障害の労災認定基準では、業務による心理的負荷の強度が「強」であれば、労災と認定されます。
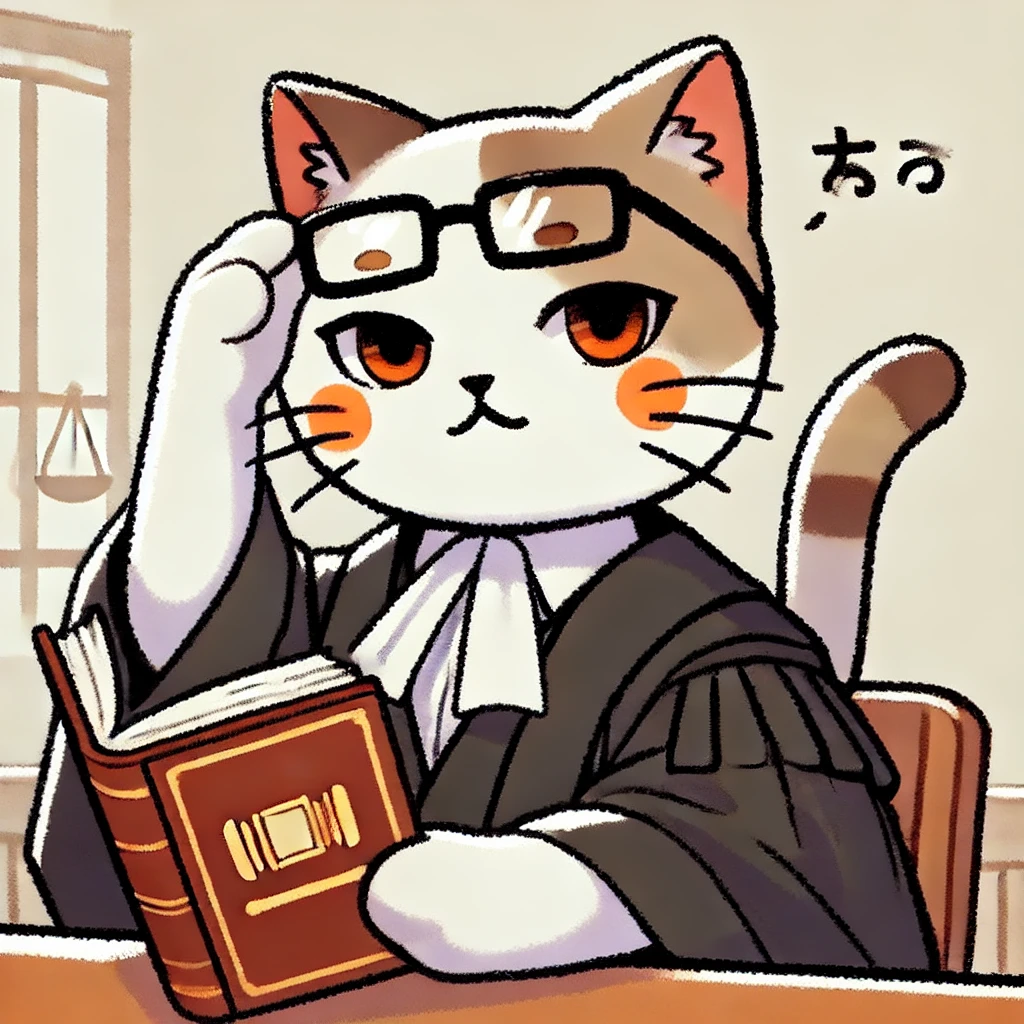
詳細は、以下の「心理的負荷の評価の仕方」を参照
この心理的負荷の強度を誰を基準にして判断するのか?という問題があります。というのも、ストレス耐性の強い人もいれば、弱い人もいます。そのため、同じ出来事でも人によって、心理的負荷の強度が異なるからです。
労災の認定基準では、精神障害を発病した労働者本人ではなく、職種・職場における立場や職責・年齢・経験等が類似する同種の労働者を基準としています。
たとえば、労災請求している労働者が、新卒採用され、従事する業務に対する経験のない労働者の場合の、同種の労働者は、業務経験がない新卒採用の労働者です。
裁判で争われる同種労働者の意味
同種労働者とはどういう労働者なのか?ということが、少なからず裁判で争われてきました。裁判例は次の3つに大別することができます。
①当該労働者と同種の業務に従事し遂行することを許容できる程度の心身の健康状態にある者を平均的労働者とする
この見解に立った裁判例としては、日本トランスシティ事件(名古屋地裁平成21年5月28日判決)、ダイハツ長崎販売事件(長崎地裁平成22年10月26日判決)を挙げることができます。
②当該労働者と職種、職場における立場、経験等の点で同種の者で、何らかの個体側の脆弱性を有しながらも、特段の勤務軽減を必要とせずに通常業務を遂行できる者を平均的労働者とする
この見解に立つ裁判例としては、ヨコハマズボルタ事件(東京地裁平成24年11月28日判決)、富国生命事件(鳥取地裁平成24年7月6日判決)などが挙げられます。
③同種労働者のうち、その性格傾向が最も脆弱な者を基準とする
この見解に立つ裁判例は、中部電力事件(名古屋地裁平成18年5月17日判決)、ジェイフォン事件(名古屋地裁平成23年12月24日判決)などが挙げれられます。
なお、ここでいう同種労働者とは、②の平均的労働者と同じ意味です。また、最も脆弱といっても、同種労働者の性格傾向の多様さとして通常想定される範囲内の者をいうとされています。
同種労働者の主張にあまり意味はない
心理的負荷の強度を誰を基準とするのか?は、結局のところ、平均的労働者を基準とするのか?平均的労働者のうち最も脆弱な者を基準とするのか?という問題です。
理論的には、上記③の平均的労働者のうち最も脆弱な者を基準とする方が、心理的負荷の強度は強く認められます。
しかし、まずは、業務上のある出来事が、心理的負荷を受けるものであったとことを証明するのが重要です。これが認定されれば、心理的負荷がどの程度の強さなのか?は評価の問題です。つまり、労働者としては、誰を基準に判断するのか?に重点を置くより、端的に、業務による強い心理的負荷があったことを主張・立証していく方がいいのではないでしょうか。
なお、裁判例の傾向は、全体的に、労災認定基準を参考にしつつ、認定基準よりは緩やかな判断を示していると言われています。