頸肩腕症候群の再発に関して、使用者の安全配慮義務が問題になった裁判例を紹介します。
日本メール・オーダー事件(東京地裁平成16年7月29日判決)
会社の従業員が、業務に起因して発症した頸肩腕症候群による長期休職から復職した後に、頸肩腕症候群を再発した事案です。
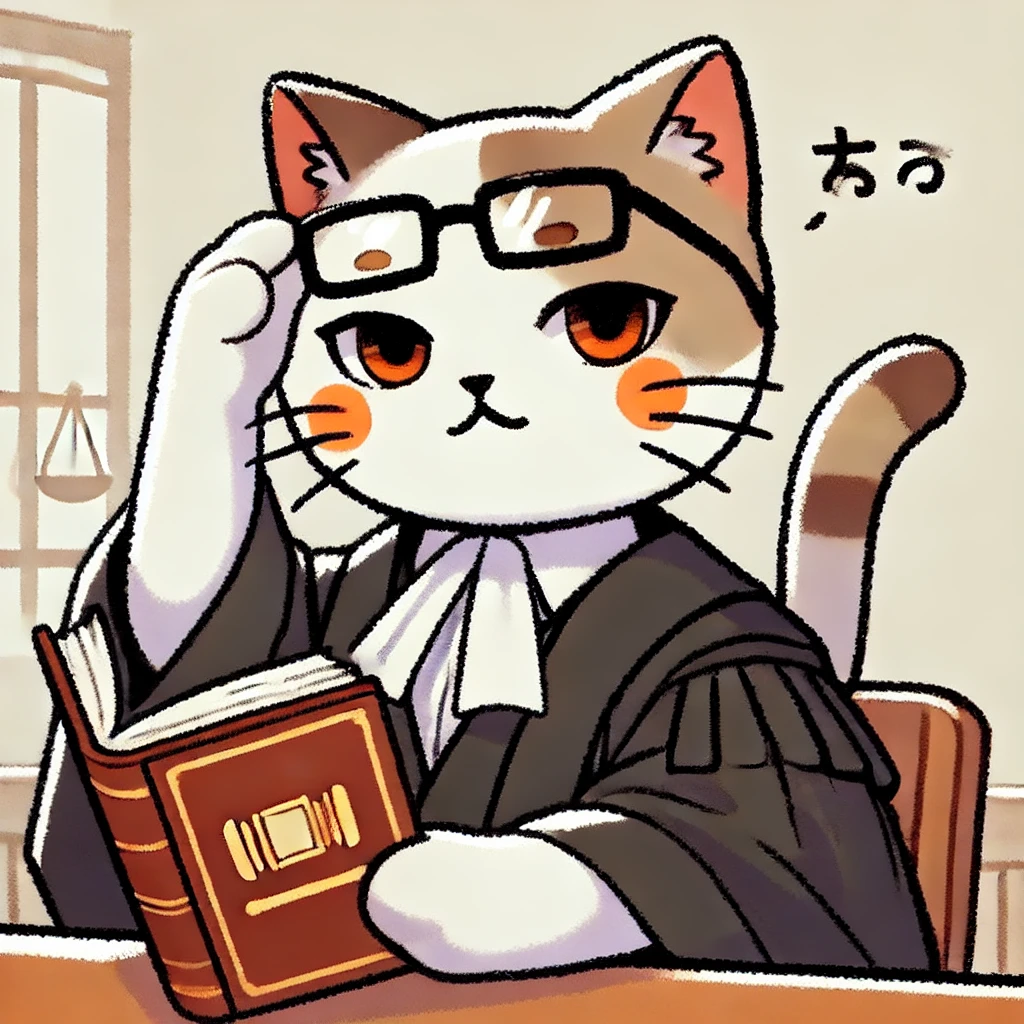
頚腕症候群については、以下の「上肢障害の労災認定」を参照
頸肩腕症候群の再発について、使用者の安全配慮義務違反が問題になりました。
事案の概要
被告は、消費者金融業、レコード及び録音済テープ並びにこれらに関連する製品の委託製造、販売及び輸出入業務等を目的とする資本金3億円の株式会社である。
原告は、昭和37年11月1日、被告の前身である会社に就職し、その後約13年の休職期間を経て昭和62年1月5日被告に復職し、平成13年3月31日に定年退職した。
原告は、管理課タイプ係筆耕校正の担当となった約1年9か月後である昭和49年3月13日、O病院のU医師により、頸肩腕障害を発症しており、1か月の休業加療を要する旨診断されたため、同月19日から欠勤し、被告に対し、同月25日、頸肩腕障害を理由に同月19日から同年4月18日まで欠勤する旨の欠勤許可願を提出し、さらに同月18日、頸肩腕障害を理由に同月19日から同年5月20日まで休職する旨の休職願を提出した。被告は、これを受けて、同年4月19日、原告に対し休職を命じた。
原告は、休職を開始してから約13年後である昭和62年1月5日、被告に復職し、第1事業部通信販売サービス係に配属された。
原告は、平成3年4月1日、第2事業部キャッシング貸付部門ベリファイ係に異動したが、その約1年7か月後である平成4年11月18日、S病院のW医師により、頸肩腕症候群を再発している旨診断された。原告は、平成4年12月1日、第2事業部督促係に異動し、平成5年6月28日、同係からベリファイ係に、平成8年2月13日、同係から商品管理部第2課に、平成12年6月21日、同課から再びベリファイ係に異動した。
原告は、休職を開始した後である昭和49年8月24日、品川労働基準監督署長により、業務により頸肩腕障害を発症したと認定され、労災保険法に基づき療養補償給付の支給決定を受けた。原告は、その後昭和58年春ころまでその支給を受けていたが、そのころ症状固定を理由に支給がされなくなったため、同年6月21日、品川労働基準監督署長に対し、再度、療養補償給付を請求した。しかし、同署長は、同年7月9日、原告が請求の理由としている疾病は同年3月31日既に症状が固定し、治癒したと認められるとして、不支給の決定をした。
そこで、原告は、労働保険審査会に対し、再審査請求を行ったが、同審査会は、昭和63年12月5日、同請求を棄却した。
原告は、平成5年6月25日、品川労働基準監督署長に対し、労災保険法に基づき障害補償給付を請求した。同署長は、同年7月19日、同法42条の規定による消滅時効が昭和63年3月31日に完成しているとして不支給の決定をしたが、平成9年2月5日、原告に対し、労働者保護の観点から不支給決定を取り消す旨通知した。そして、原告は、品川労働基準監督署の指示に基づき、労災病院で診察を受けた後、同署長により、後遺障害等級12級12号に該当する旨の認定を受け、同年12月17日、障害補償一時金92万8,000円、障害特別支給金20万円、障害特別一時金15万7,092円の支給決定を受けた。
復職した原告が従事した第1事業部通信販売サービス係の業務内容は、通信販売を行っている商品の申込み事務と入金処理であり、上肢を固定して作業をしたり、同じ腕や手を反復して使う作業もほとんどなかった。原告は、筋肉の付け根が痛むとき等にたまに鍼治療を受けることがあったものの、症状は安定し、体調も良くなっていた。
そして、原告は、復職して約5か月後の昭和63年6月に実施された社内定期健康診断においては、担当医師に対し、身体の調子は良好であり、頸肩腕症候群は治癒している旨述べた。
なお、平成元年から平成10年までの間、被告が毎年実施している社内定期健康診断において、原告が、担当医師に対し、肩や腕の痛みを訴えたことの記録はない。
被告は、原告が復職して4年が経過した平成3年1月11日、ローン事業拡大のため、原告をベリファイ係の補助としてその業務に就かせ、同年4月1日、正式にベリファイ係に異動させた。原告をベリファイ係に異動させた後、被告は、社員を1名新たに雇用するとともに、派遣社員1名の派遣を受ける契約を締結して、従前、原告が従事していた業務に従事させた。
原告は、ベリファイ係に異動を命じられた当時、頸肩腕症候群が再発するのではないかと不安になったが、それを被告に申し出なかった。
原告は、ベリファイ係に異動した後、頭部の付け根、首、肩、腕に痛みと凝りを感じるようになった。このため、仕事中に、固まった部分や凝った部分をプラスチックハンマーで叩いたり、右手にしびれや痛みを感じるようになった後は、サポーターをはめ、さらに、エアコンの風が身体に直接当たると痛みが増すことから、夏季も長袖服を着用した。
原告は、平成4年8月ころからは、右頸部、頭部の付け根に凝りと痛み、右肩に固まりと凝り、右手指にしびれを感じるようになった。特に、ボールペンによる筆記時やホッチキスの使用時に、親指の付け根から肩の筋に痛みが走った。また、家事においても、包丁やフライパンを持つのがつらく、洗濯物をよく落とす等のことがあった。朝、起床時、両手はしびれ、次第に、土曜日及び日曜日に休息してもしびれは残ったままで回復しなくなった。また、原告は、S町針灸院に、平成3年8月29日から5回、同年9月11日から5回、通院した。
原告は、平成4年11月18日、しびれが治らないため、S病院で受診し、W医師に対し、項背部、両腕の凝り、だるさ、右手首伸側の痛み、脱力等を訴えた。W医師は、原告の主訴内容、約7年前に頸肩腕症候群により通院加療を受けたことがあること、平成3年4月に現在の職場に異動し、その後、平成4年8月ころから症状が悪化し、最近では症状が非常に強くなってきているという経過、さらに、診察の結果、項背部、頸部から両上肢の筋硬・圧痛が著明であり、右(手関節部)外側茎状突起部に圧痛があること、握力計測の結果、右握力14㎏、左握力19㎏と低下していること、エキスパンダー検査が右腕の痛みのため実施できなかったこと、頸椎運動制限は認められず、頭部圧迫試験は陰性であり、頸椎椎間板症が否定されたこと等を総合して、頸肩腕症候群の再発であり、当面2か月間は軽減業務、通院加療を要する旨診断した。原告は、W医師から、休職して治療することを勧められたが、収入が減ることによる経済的な問題、再度休職することによる不利益を心配して、休職しなかった。
原告は、その後もS病院に通院し、機械器具による運動療法、体操指導による運動療法、ホットパック、パラフィン浴、マイクロ波の照射、徒手筋力テスト、療養指導を受けた。
原告は、S病院のW医師により前記エのとおり診断を受けたが、被告に対し、診断書を添えて、頸肩腕症候群が再発したことを申し出なかった。
しかし、平成4年11月、訴外組合は、年末一時金闘争に際し、被告に対し、第2事業部のベリファイ担当者に実施されている月6回の残業スケジュールを止めることを要求するとともに、原告が頸肩腕症候群を再発したことを告げた。
原告は、平成4年12月1日、督促係に異動したが、平成5年6月21日、督促係から再びベリファイ係への異動を告げられ、同月28日、同係へ異動した。
原告は、再びベリファイ係に異動する前に、平成5年2月ころからベリファイ係の補助としてベリファイ業務に従事していたところ、体調を崩し、眠れない日が続くようになったため、就寝前に睡眠薬を飲むようになった。そして、正式にベリファイ係に異動した同年6月28日ころには、右上腕部、左肩、首、背中等の痛みがひどくなり始めた。S病院においてリュウマチ検査をしたが問題はなく、W医師は、頸肩腕症候群によるしびれと診断した。
平成5年春の春闘において、訴外組合は、原告が一昨年より頸肩腕症候群を再発している、原告の頸肩腕障害は、就労中に再発したものであり、健康回復のために企業として責任を取ること、第2事業部(ローン係)の新規貸付け担当の部署では、電話の応対のほか筆耕作業があって、電話交換手よりも苛酷な業務であり、とりあえず、電話交換手並みの休息時間を導入すること等を申入れたが、被告は、ベリファイ業務は苛酷なものとは考えていない等と回答した。
原告は、平成8年2月13日、ベリファイ係から商品管理部第2課に異動し、平成12年6月21日、同課からベリファイ係に異動した。
原告は、商品管理部第2課からベリファイ係に異動する際、約半年後には定年退職となることもあって、異動を拒否しなかった。
裁判所の判断
裁判所は、会社の安全配慮義務違反を肯定しました。
原告が先に発症した頸肩腕症候群は、原告が復職する相当前にその症状が固定し、その後さらに症状が軽快して、遅くとも昭和63年6月には、それ以前に後遺障害として神経症状が残存していたとしても、それも消失していたが、平成3年4月1日以降、ベリファイ業務に従事したことにより、遅くとも平成4年11月18日までに治療が必要な状態に再度至ったものであり、頸肩腕症候群が再発したものと認めるのが相当である。
頸肩腕症候群は、症状が軽快又は治癒しても、悪化又は再発しやすい傷病であること、ベリファイ業務は、電話応対しながら、筆記するという作業を就業時間中ほぼ常時行うものであり、少なくとも頸肩腕症候群の発症歴を有する原告にとっては、右手ないし右上肢等を酷使し、過重な負担になると評価すべきものであることからすれば、被告は、復職した原告を、そのようなベリファイ業務に従事させるべきではなかったし、また、仮にベリファイ業務に従事させるとしても、事前に原告から症状等について事情を聴取し、または、医師の診断を受けさせる等慎重に対応すべきであったし、さらに、ベリファイ業務に従事させた後も、原告の頸肩腕に変調がないか等に十分に配慮し、変調があった場合には、直ちに頸肩腕に負担の少ない業務に配転する等の措置を講ずべき注意義務があったというべきである。
被告は、原告を、平成3年1月11日、ベリファイ係の補助としてその業務に就かせ、同年4月1日、正式にベリファイ係に異動させたが、ベリファイ業務に従事させるに当たり、当時の原告の症状について、原告から事情聴取することも含めて何ら調査を実施しておらず、また、ベリファイ係に異動させた後、平成4年12月1日までの1年8か月(補助としてベリファイ業務に従事するようになった平成3年1月11日からは約1年10か月)にわたりベリファイ業務に従事させた上、残業の割当てもしている(特に、原告が頸肩腕症候群を再発したと診断された平成4年は、1月が14.0時間、2月及び3月が各10.5時間、9月及び11月が各11.0時間と、他の年と比較すると残業時間が多い。)。また、被告は、原告をベリファイ係に異動させた後も、原告から変調がないか等について事情聴取をしたことも認められないばかりか、原告は、ベリファイ係に異動した後、頭部の付け根、首、肩、腕に痛みと凝りを感じるようになっため、仕事中に、固まった部分や凝った部分をプラスチックハンマーで叩いたり、サポーターをはめ、エアコンの風を避けるため夏季も長袖服を着用していたが、被告の管理職であったA、B及びCは、原告に変調があれば気付くような位置関係に席が配置されていたから、このような原告の変調に気付いてしかるべきであるのに、これに気付かず、何らの対応策も講じなかった。
さらに、平成4年11月、訴外組合は、年末一時金闘争に際し、被告に対し、原告が頸肩腕症候群を再発したことを告げたところ、被告は、その理由はともかく、同年12月1日に原告を督促係に一度異動させたが、平成5年2月ころから再び補助として原告をベリファイ業務に従事させ、同年6月21日、正式に督促係から再びベリファイ係に異動させた。そして、平成5年の春闘においても、訴外組合は、原告が一昨年より頸肩腕症候群を再発している等と告げたが、被告は、ベリファイ業務は苛酷なものとは考えていない等と回答した。以上の事実によれば、被告は、平成5年2月以降に原告をベリファイ業務に従事させた際にも、原告から事情聴取することも含めて何ら調査を実施しておらず、また、異動させた後もそのような調査をしていないことが認められる。
そうすると、被告には、復職した原告を、ベリファイ業務に従事させるべきではなかったのに従事させ、また、ベリファイ業務に従事させる前に原告から症状等について事情を聴取する等せず、しかも、ベリファイ業務に従事させた後も、原告の頸肩腕に変調がないか等に十分配慮しなかった点において、安全配慮義務違反があったといわざるを得ない。