海外業務において、感染症にり患した場合、労災と認定されますか?
海外業務による感染症と労災
出張や海外派遣のように、事業主の元を離れて業務に従事する場合でも、事業主の包括的又は個別的な指示・命令に従って業務を行っている以上、事業主の支配下にあると言えます。
出張の場合、命令が出て事業場を離れてから業務を終えて事業場に戻るまで、業務の成否・遂行方法等について、包括的に事業主の支配を受け、事業主に対して責任を負っていると解されます。したがって、出張の全過程に、業務遂行性が認められます。
ただ、出張の場合、事業主の管理下を離れているので、その間の個々の行為については、事業主の拘束を受けず、労働者に任されています。出張中に、様々な私的行為が行われます。もっとも、出張の性質上、ある程度の私的行為が行われることは、通常、想定されています。したがって、積極的な私的行為にわたる場合を除き、出張中に行われる食事、宿泊、入浴等の出張に当然又は通常伴う範囲の行為も含めて、業務遂行性が認められます。
伝染病が流行している地域・国や風土病のある地域・国に、出張し、伝染病や風土病にり患した場合、業務遂行中に病原体に汚染されて、り患したことが明らかに認められる場合は、業務起因性が否定される特別な事情がない限り、業務上疾病として労災と認定されます。
上記は、海外における業務の場合にも当てはまります。ただし、海外出張か海外派遣かによって、労災保険の取扱いが異なります。
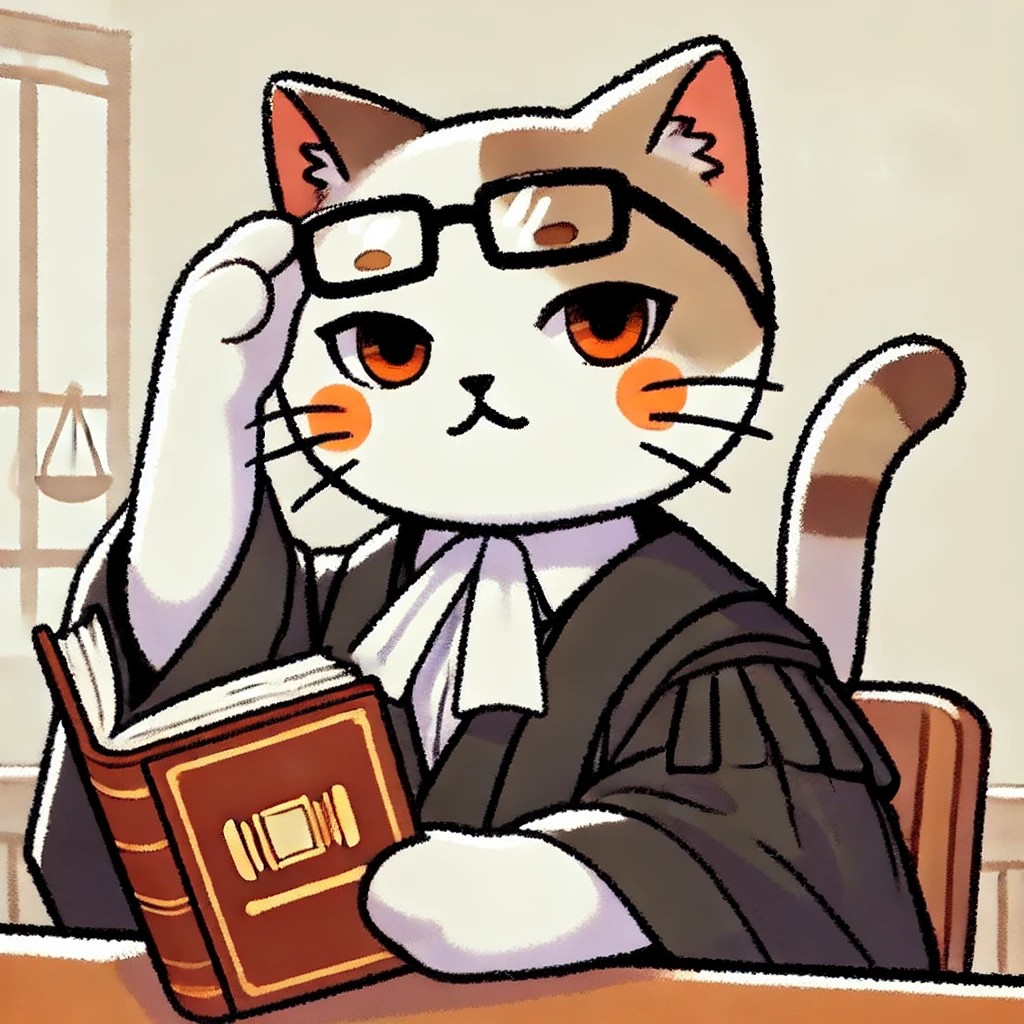
詳細は、以下の「海外赴任者の労災」を参照
海外における業務による感染症の取扱いについて(昭和63年2月1日付基発第57号)
海外業務によって、感染症にり患した場合に、労災と認定されるか?という問題について、厚労省の通達があります。
通達には、業務と感染症との因果関係について、専門委員会の検討結果が示されています。
基本的な考え方
海外においてり患した感染症については、業務起因性が認められる場合は、当然、労災と認定されます。個々の事例について感染経路・潜伏期間・臨床症状・診断・業務との関連等を十分調査・検討することとされています。
感染症と業務との関連
通達は、感染症と業務との関連について、感染リスクの観点から次のように分類しています。
①媒介動物と接触の多い業務において感染リスクの高い感染症
媒介ネズミ・媒介昆虫等の媒介動物感染により間接伝播する感染症であって、媒介動物と接触の機会の多い次の業務は、感染リスクが高いと考えられるが、これらの感染症については、媒介動物と接触の機会の多い業務が他の業務に比較して感染リスクが高いと指摘されるものであって、他の業務及び一般生活においても感染リスクは存在するものであるので、業務起因性の判断に当たっては、感染経路・潜伏期間・臨床症状・診断等を十分調査・検討することとされています。
具体的な感染症としては、以下のものが挙げられています。
媒介動物と接触の多い業務において感染リスクの高い感染症の具体例
(1) ペスト:媒介動物の多い山林地域や船舶内での業務
(2) 黄熱(森林型) :媒介動物の多い山林地域での業務
(3) 住血吸虫症:媒介貝の棲息する河川内での業務
②業務遂行中及び一般生活に同様の感染の機会がある感染症
汚染飲食物等の媒介物感染により間接伝播する感染症・媒介動物感染により間接伝播する次の感染症及び気道感染する真菌感染症は、侵淫地域(当該感染症への感染リスクが高い地域)において、業種や業務内容とは無関係に業務遂行中に感染の機会があるが、感染リスクは、一般生活においても同様に存在するので、ただちに業務上疾病と認めることはできないとされています。
業務遂行中及び一般生活に同様の感染の機会がある感染症の具体例
(1) 媒介物感染:コレラ・細菌性赤痢・腸チフス・パラチフス・A型肝炎・非A非B型肝炎(水系感染)・アメーバ症・ジアルジア症
(2) 媒介動物感染:デング熱・日本脳炎・狂犬病・ラッサ熱・黄熱(都市型)・発疹チフス・発疹熱・マラリア・トリパノソーマ症・リーシュマニア症・フィラリア症・オンコセルカ症
(3) 気道感染:コクシジオイデス症・ヒストプラスマ症・ブラストミセス症・パラコクシジオイデス症
③医療・研究業務を除いて感染リスクの高い業務が存在しない感染症
次の感染症については、「患者の診療若しくは看護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務」を除いて、特に感染リスクの高い業務はないので、通常、これらの業務以外については、業務上疾病と認められないとされています。
医療・研究業務を除いて感染リスクの高い業務が存在しない感染症の具体例
(1)血液・体液等の接触感染:B型肝炎・デルタ肝炎・非A非B型肝炎(血液感染)・後天性免疫不全症候群(AIDS)
(2) 媒介動物感染:腎症候性出血熱
④その他
アフリカ出血熱(マールブルグ病)については、ウイルスの生態が未だよく解明されておらず、業務との関連も不明なので、本省に稟議することとされています。